学習指導要領(平成30年告示)が重視する「数学的活動」については、以前の記事“【数学的活動】とは数学の学び方を考える”で理論的な背景を紹介しました。今回はその続編として、私自身が授業で実践してきた「数学的活動」を、以下の3種類の活動に分けて紹介します。
- 問題を作る活動
- 現実の世界で数学を発見する活動
- 現実の事象が数学化できるか検討する活動
これらの活動は、単なる知識の習得にとどまらず、生徒の探究心や思考力、表現力を育てる上で大きな効果をもたらしました。本記事では、それぞれの活動がどのように授業に組み込まれ、生徒の学びにどのような変化をもたらしたのかを具体的に紹介していきます。
問題を作る活動:数学の「問い手」になる経験
数学の授業では、多くの時間が「問題を解くこと」に費やされがちです。しかし、「問題を作る」ことは、解く以上に深い理解と思考力を必要とする創造的な活動です。私は単元のまとめやテスト前の振り返りのタイミングで、生徒自身に「この単元の知識を使った問題を自分で作る」課題を出しています。
活動の手順と工夫
- 生徒に「二次関数の最大・最小」「三角比と面積」など、学んだテーマに基づいて問題をつくらせる
- 解答と解説もセットで提出させることで、自分の理解を再構築させる
- 参考にした問題を明示させることで、引用のルールなどを体感でき、大学入試などの先取りをできる
- 他の生徒の問題を解き合う「相互出題」や、優秀作品をクラス内で紹介する時間を設ける
すぐに取り組みやすい理由
この活動は、教科書を進めることで精一杯という先生にも非常におすすめです。なぜなら、授業時間を確保しなくても、宿題として取り組ませることができるからです。また、単元を通じての学びの振り返りや、テスト前のアウトプット活動としても効果的です。
たとえば、「テスト対策として問題を解くだけではなく、自分で作ってみよう」と促すことで、知識の定着を促すだけでなく、どの部分を理解していないかの自己点検にもつながります。
学びの効果
生徒たちはこの活動を通して、「この条件を入れると解けるけど、抜くと成立しない」など、問題成立のための論理構造を自然と意識するようになります。また、自分の問題を友人に解いてもらう過程では、他者の視点や多様なアプローチに触れる機会にもなり、相互的な学びが生まれます。
現実の世界で数学を発見する活動:数学の「見方」で世界を見る
教科書や問題集の世界から一歩外に出て、現実社会に潜む数学を生徒自身が発見することは、数学の学習に対する「気づき」や「驚き」を生み出す非常に有効なアプローチです。
活動の内容とねらい
この活動では、まず生徒に「日常生活の中にある数学的な事象を探す」よう促します。たとえば次のような視点が挙げられます。
- 階段の勾配と三角比の関係
- スーパーの割引表示に潜む割合や関数的変化
- SNSやニュース記事に出てくる統計グラフの読み解き
- 建物の対称性や黄金比
- 宝くじの金額
一見すると数学とは関係なさそうな場面に、数理的構造があることに気づかせることで、生徒たちは「数学って意外と身近にあるんだ」と感じるようになります。
教育的意義
この活動の最大の意義は、「数学的な見方・考え方を働かせて現実社会を見る力」を育てることにあります。生徒は、単なる知識としてではなく、“ものの見方”として数学を捉え直すようになります。
また、学習指導要領が掲げる「見方・考え方を働かせる」という観点においても、この活動は非常に有効です。生徒は、現実の課題に対して「何が変数となりうるか」「どのような数学的構造が背後にあるか」などを自ら考えるようになります。
授業への組み込み方
この活動は、自由課題やレポート課題、探究活動の導入としても取り入れやすいのが特徴です。また、学級活動や総合的な探究の時間と関連づけて実施することで、教科横断的な学びにも発展させることが可能です。
生徒の声・変化
- 「数学って机の上だけの話だと思っていたけど、毎日の生活にも使われてるんですね」
- 「見方が変わると、いつも通る道が違って見えるのが不思議だった」
こうした言葉からもわかるように、数学を「学ぶ対象」から「世界を読み解くツール」へと昇華させるのがこの活動の醍醐味です。
現実の事象が数学化できるか検討する活動:モデル化する力を育てる
「現実を数学で表すことはできるのか?」という問いは、数学的活動の中でも特に高度で、本質的な学びを引き出すテーマです。
生徒が日常的に学ぶ教科書の文章題は、すでに数理化された現象を解く形式になっていますが、そこからさらに一歩踏み込んで、「この数学は現実のどんな場面に応用できるのか?」を考えさせることが、この活動の出発点です。
活動の方法と展開例
- 教科書の文章問題を題材に、逆にそのような数理構造をもつ現代的な事象を考える(例:2次関数 → 販売価格と売り上げの数理モデル)
- 社会的な課題に対して、どのような数理モデルで表現できるかをグループで議論させる(例:感染症の拡大予測、気温と電力使用量の関係)
さらに発展させる場合は、実際のデータや仮定条件を用いて、数式モデルを立ててみることにも挑戦させます。
数学化するとはどういうことか
現実を数学化するとは、「すべてを正確に再現する」ということではなく、本質的な構造に着目してモデルを作ることです。
その過程では、
- 何を変数とし、何を定数と見なすのか
- どの程度まで簡略化(理想化)するのか
- どこに限界があるのか
といった、数学と現実をつなぐ批判的な視点が求められます。
生徒の学びの変化
この活動を通じて、生徒は「数学を使って説明するとはどういうことか」を実感するようになります。単に計算するだけでなく、
- 「この関数の傾きは何を意味するのか?」
- 「初期値を変えたら現象はどう変化するのか?」
- 「このモデルはどこまで信頼できるか?」
といった深い思考や仮説検証の力が育まれます。
教師のサポートとして
こうした活動では、あらかじめ「題材の背景となる社会課題」や「必要な数学的知識」に関するミニレクチャーを組み込んでおくことで、生徒の思考がスムーズに展開します。また、ICTツールやスプレッドシート、グラフ作成アプリなどを活用することで、可視化・実験的アプローチが可能となり、数学化の面白さを一層引き出すことができます。
おわりに:数学的活動は、生徒の「学ぶ意味」をつくり出す
ここまで紹介してきた
- 問題を作る活動
- 現実の世界で数学を発見する活動
- 現実の事象が数学化できるか検討する活動
という3種類の活動は、いずれも数学を「知識」から「思考の道具」へと昇華させるプロセスを含んでいます。
生徒たちはこれらの活動を通じて、公式を機械的に使うだけでなく、数学の意味を問い直し、使いこなす力を少しずつ身につけていきます。
また、数学的活動は、「なぜ学ぶのか?」という根源的な問いに対して、生徒自身が答えを見つける手段にもなります。
教員側から見ると、こうした活動は一見ハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、
- 授業時間内に限らず、宿題や振り返りとして活用できること
- 小さな問いからでも始められること
- 生徒の気づきを出発点にできること
などから、日々の授業に自然に取り入れることが可能です。
VUCA時代、そしてSociety 5.0の社会を生き抜く生徒たちにとって、答えのない問いに挑む力は不可欠です。数学的活動は、その力を育むための強力な教育実践です。
教師が「教える人」から「学びの環境をデザインする人」へと役割を転換する中で、数学的活動は、探究的で創造的な学びを生み出す重要な鍵となるでしょう。

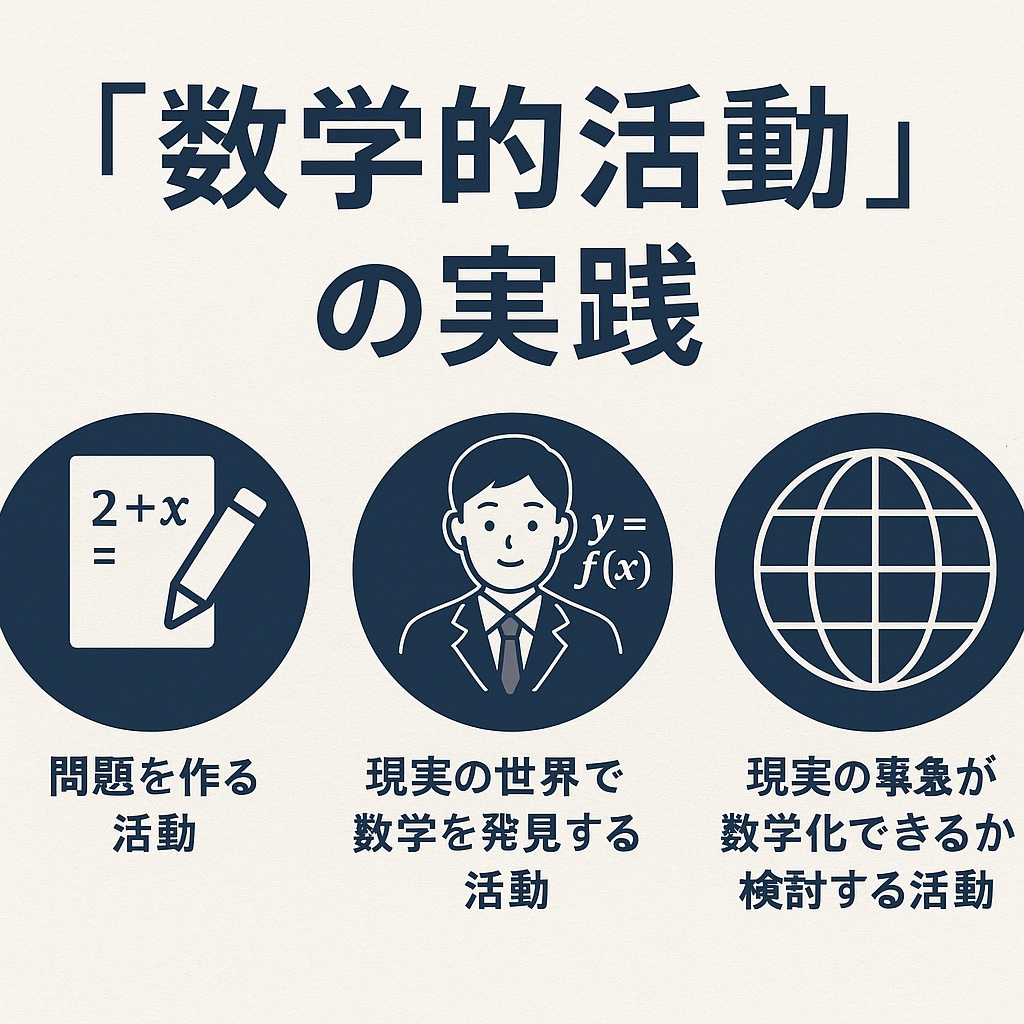
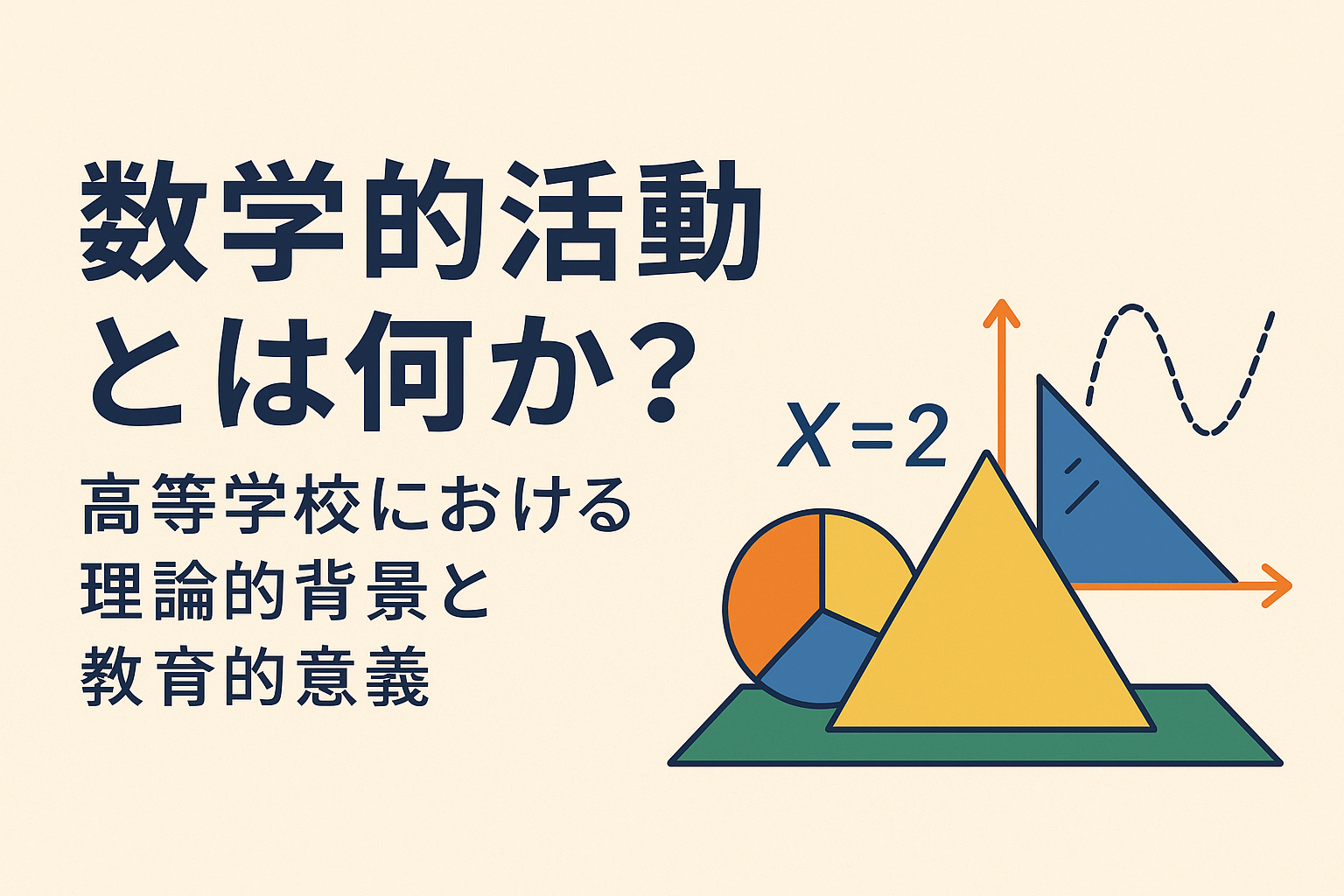

コメント