私は、いきなり学校全体の探究の責任者を任され、全学年のカリキュラムを再構築することになりました。
この記事では、探究担当になった先生が「最初に押さえておきたいポイント」を、段階的に整理してご紹介します。

Step 1:なぜ、今「探究」なのか? — VUCA時代とSociety 5.0
探究が教育現場で重視されるようになった背景には、「VUCA(ブーカ)」と呼ばれる時代状況があります。
- Volatility(変動性)
- Uncertainty(不確実性)
- Complexity(複雑性)
- Ambiguity(曖昧性)
技術革新やグローバル化、価値観の多様化が進む中、予測困難な未来を生き抜くために、かつてのような「正解を覚える学び」だけでは通用しません。
求められるのは、
- 「問いを立てる力」
- 「調べて深める力」
- 「他者と協働しながら考える力」
- 「自分の価値観と社会の接点を見つける力」
といった “探究的な資質・能力” です。
経済産業省が提唱する「Society 5.0」でも、AI・IoTといった先端技術と人間の創造性・主体性の融合が求められています。
探究とは、こうした未来社会に対応できる学びの土台を育てる時間なのです。
📺 参考:日本経済団体連合会「Society 5.0」紹介動画
Step 2:「探究」の目標と、学校教育目標との接続
文部科学省による「総合的な探究の時間」の教科目標は、以下のとおりです。
探究の見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して,
自己の在り方・生き方を考えながら,よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を育成する。
ここで注目したいのは、「自己の在り方・生き方を考えながら」という視点です。高校での探究は、単なる課題解決ではなく、「自分はどんな人間で、どんな社会との関わり方をしていきたいのか」 を見つめる時間でもあります。
加えて、各学校には固有の教育目標があります。たとえば、上海日本人学校では、
「志を高くして自ら学ぶ国際人の育成」
という教育目標が掲げられていました。
この目標と探究をどう結びつけるかを考えると、たとえば
「国際的な視野で課題を捉え、自らの志をもとに社会課題へ主体的に関わる力を育てる」
といった探究の方向性が導き出せます。
つまり、探究は学校の教育理念や特色と深く結びついた学びであるべきなのです。

Step 3:探究の入り口は“いつでも・どこでも
特に高校1年生では、次のような意識づけを大切にしました。
- 「探究は特別な活動ではなく、日常の中にある」
- 「各教科・学校行事・部活動など、すべてが探究の素材になりうる」
たとえば、行事を通して自分のリーダーシップの在り方に気づいたり、授業中の学びから「もっと深く知りたい」と思ったりする経験が、すでに“探究の芽”なのです。
「いつでも、どこでも、誰とでも学びはつながる」そうした感覚を持たせることが、高校1年生にとっての“探究の第一歩”になります。
Step 4:探究は“サイクル”で成長する
探究は「課題を見つけて、調べて、発表して終わり」ではありません。以下の 探究のサイクル を繰り返すことが、深い学びにつながります。
- 問いを立てる
- 調べる
- 考える
- 発表する
- 振り返る(そして、問い直す)
このサイクルを、最低でも年間3回程度は意識的に回すようにしましょう。
- 高校1年生では「探究の型を身につけること」
- 高校2年生では「実社会での探究や、他者を巻き込む経験」
- 高校3年生では「自己の進路や将来に向けてまとめ上げること」
がそれぞれのステージでの目標となります。担当教員の大切な役割は、「生徒が自分の問いに気づき、やってみようと思える状態」に導くことです。

おわりに
「探究」は、決まった正解も、正解の出し方もありません。だからこそ、生徒一人ひとりの可能性を広げ、社会との接点をつくる教育の中心になります。
そして、教員自身もまた“探究的”であることが求められる時代です。探究は、私たち教員にとっても「理想の教育」を実現するための有力な手段になり得ると感じています。
最初は不安でも、「問いから始まる学び」を丁寧に積み重ねていくことで、きっと大きな実りへとつながります。




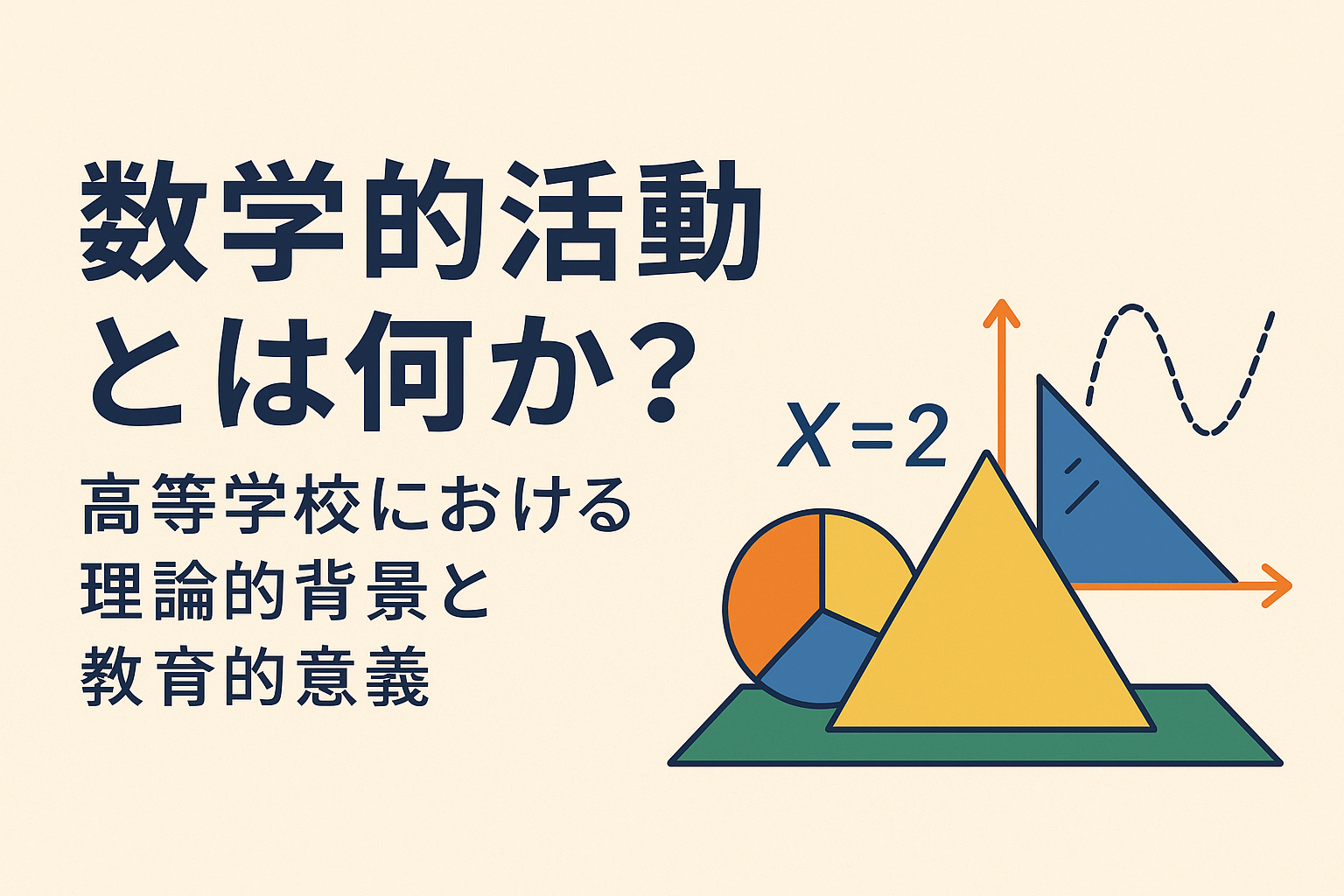
コメント