導入 ― 男子と女子、どちらが生まれやすい?

男子と女子、どちらのほうが生まれやすいでしょう?
このシンプルな発問から、授業は始まりました。今回の記事では、2024年度に日本人学校で行った国際理解教育の実践をご紹介します。
私が国際理解教育で大切にしているのは「気づき、理解し、尊重する」という流れです。中国に暮らす日本人生徒が、自分たちの周囲や世界の現実に「気づき」、その背景を「理解」し、異なる価値観を「尊重」できるようになることを目指しています。
性比とは?
性比とは、出生時における男子と女子の比率を指し、通常は男子出生数 ÷ 女子出生数で表します。
世界の自然な平均値は1.05(男子105人:女子100人)前後ですが、国や地域によっては、この比率が大きく外れることがあります。
日本のデータを見て考える
授業の冒頭、私は黒板に日本のデータを書きました。
日本(2022年)… 男子:421,934人、女子:402,648人
性比 = 1.048

男子のほうが少し多く生まれていますね。なぜだと思いますか?

男子は体力的に弱いって聞いたことがあります。だから、生まれるときに多めになってるのでは?

その通りです。実は男子は性染色体がXYで、X染色体に比べてY染色体は遺伝情報が少なく、一部欠損している状態です。このため免疫や修復機能が弱く、病気や環境変化に対して女子より脆弱だと言われています。長い進化の過程で、その弱さを補うために、自然界は男子をやや多く誕生させてきたと考えられます。
データ収集 ― 世界の性比を調べる
生徒たちに、国連人口統計や厚生労働省のデータをもとに、日本、中国、インド、フランス、ナイジェリアの性比を調べてもらいました。班ごとに計算し、グラフ化します。

中国は1.1を超えてますね。男子が多すぎる。
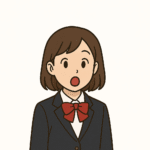
インドも同じくらいで、自然値よりずっと高い。

フランスは1.05で自然値に近いです。
班別発表 ― 国ごとの特徴
| 国名 | 性比(出生時) | 特徴・背景 |
|---|---|---|
| 日本 | 1.048 | 安定して自然値に近い |
| 中国 | 1.12 | 一人っ子政策、男児選好、妊娠中の性別告知禁止 |
| インド | 1.11 | 男児を好む文化的背景、出生前診断 |
| フランス | 1.05 | 自然値に近い |
| ナイジェリア | 1.06 | 自然値付近だが地域差あり |
背景を探るディスカッション

なぜ中国やインドの性比はこんなに高くなるのでしょう?
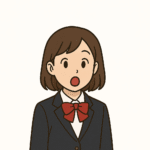
中国の一人っ子政策で、男の子を望む家庭が多かったからだと思います。

インドでは持参金制度があって、女の子は経済的に負担だと考えられるからでは?

その通りです。さらに中国では、出生前の性別選択を防ぐために、医師が妊娠中に胎児の性別を告知することは法律で禁止されています。また、インドでは女子を戸籍に登録しなかったり、ネグレクトの対象になることもあるようです。
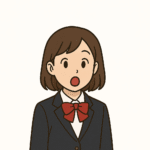
じゃあ、中国では生まれるまで性別が分からないんですね。

そうです。とはいえ、非公式な手段で性別を知ろうとするケースもあり、完全な是正には至っていません。
女子が多く生まれる地域

女子が他の地域より多く生まれる地域もあります。特にアフリカの一部地域です。

逆のケースもあるんですか?

はい。衛生環境が厳しい地域では、生命力の強い女子のほうが乳児期の生存率が高く、その結果、統計的に女子が多くなることがあります。
医療制度の違い ― イギリスの例

出生前の医療制度も国によって違います。例えばイギリスでは、妊娠中に胎児が障害を持っているかどうかを検査するスクリーニングが、国の制度で無料で行われます。これは性別判断とは別で、医療的なサポートや出産準備に活かす目的があります。

国によって、出生前の情報の扱い方も全然違うんですね。
時系列変化
日本の性比は過去50年間ほぼ1.05前後で安定。一方、中国は1980〜90年代に1.12〜1.15を記録。インドも高止まりが続いています。女子出生が多い地域はアフリカの一部で、衛生環境や医療アクセスが影響しています。
国際理解教育とのつながり
今回の授業を通じ、生徒たちは「性比」という統計が、文化・制度・医療・自然条件など多くの要因に左右されることを学びました。
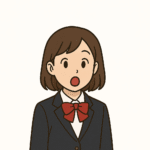
数字の背景にこんなにたくさんの要素があるとは思わなかった。

自分の国の状況は世界の中で見て初めて理解できるんですね。
学びのポイント
- 統計リテラシーの向上
- 文化・制度・医療と人口動態の関係
- 国際比較の視点
まとめ
出生数の性比は単なる数字ではなく、社会や文化、自然界の調整、そして医療制度までも反映する重要な指標です。男子出生が多い理由には、生物学的な弱さや進化的調整があり、女子出生が多い地域には環境的要因があります。
こうした学びを通して、生徒たちは「数字の裏にある物語」を読み解く力を身につけていきました。

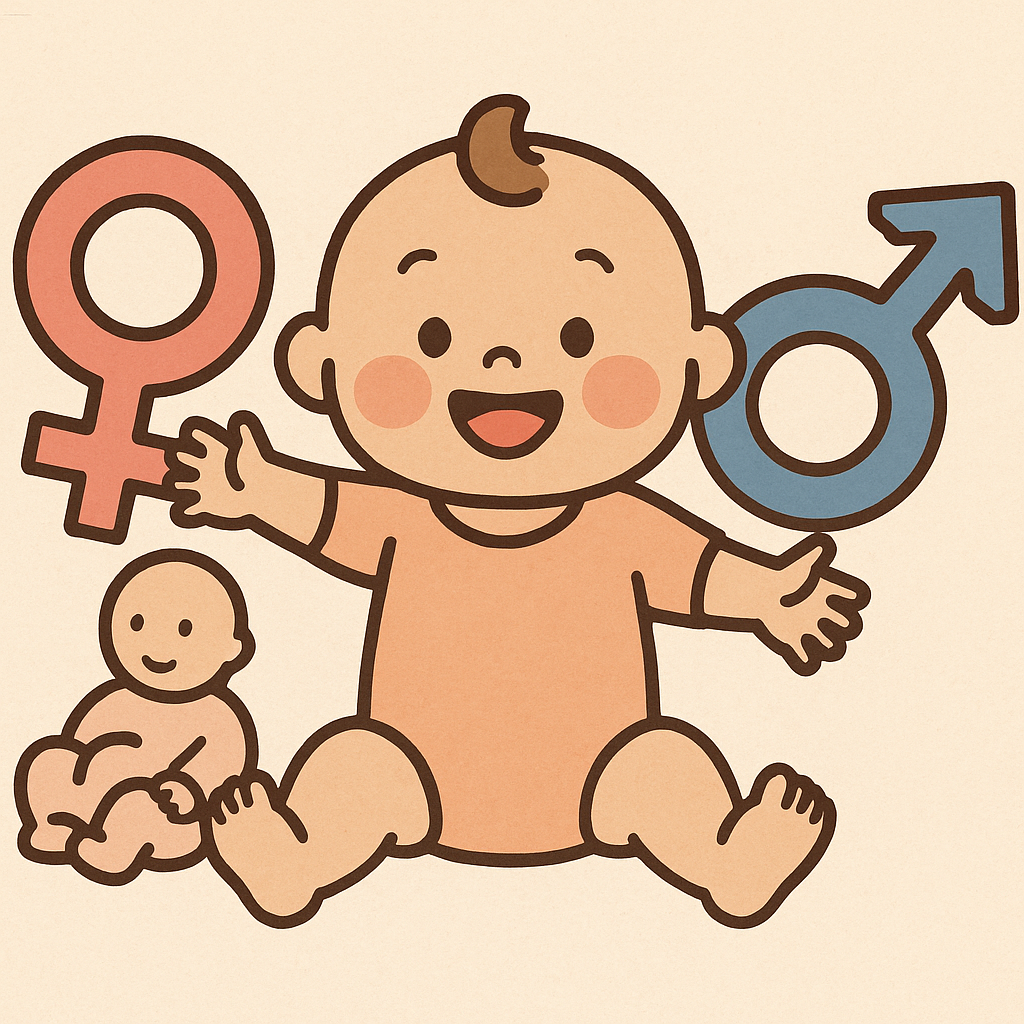


コメント