はじめに
2024年度、日本人学校の国際理解の授業において、中国の人口分布と経済格差をテーマとした授業を実践しました。この授業では、黒河・騰衝線という地理的概念を軸に、中国の社会経済構造の理解を深めることを目的としました。
授業の導入 ― 1本の線で中国を分けると…
授業の冒頭で、生徒たちにこう問いかけました。

中国の国土をちょうど2つに分ける線を引いたとき、人口はどのように分かれると思いますか?
黒板に中国地図を描き、北東部の黒河市と南西部の騰衝市を結ぶ線を引きました。これが有名な
黒河・騰衝線(ホー・トンチョン線)です。
「この線の東側には国土面積の約40%が含まれますが、人口の約90%が暮らしています。逆に西側は国土の約60%を占めながら、人口はわずか10%程度です。」
生徒たちからは驚きの声が上がりました。

え、そんなに差があるんですか?
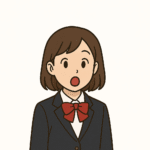
西側は山とか砂漠が多いからですか?
まさにその通りです。自然条件、歴史、そして近代以降の経済政策が、この人口分布に大きな影響を与えてきたのです。
沿岸地域の発展 ― 中国はなぜ栄えたのか
次に上海の写真を提示しました。高層ビルが並ぶ浦東新区、外灘の欧風建築群、世界屈指のコンテナ港…。
「どうして中国の沿岸部、特に上海のような都市がこれほど発展してきたのでしょうか?」
生徒たちからの反応は積極的でした。

海があるから貿易ができる!
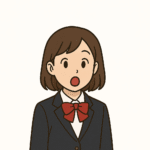
外国からお金や技術をもらえるからじゃないですか?
その通りです。沿岸部は地理的に港湾が多く、国際貿易の拠点となりやすい条件を備えていました。特に上海は19世紀後半の開港以来、外国資本や西洋文化が流入し、近代的な商業都市として発展を遂げました。
沿岸部の発展と鄧小平の戦略
なぜ東側に人口が集中しているのか。その理由のひとつが、経済の中心が沿岸部にあることです。上海、北京、広州などの都市は海に近く、古くから貿易で栄え、近代以降も外国との経済交流が盛んでした。
特に改革開放政策を推進した鄧小平は、「まず豊かになれる地域から先に発展させ、その成果を全国へ波及させる」という戦略を採用しました。その象徴が沿岸部に設置された経済特区です。
1980年に深圳・珠海・汕頭・厦門、1988年には海南島全島が経済特区に指定され、外国資本や技術を積極的に導入。輸出向け製造業や先端産業が集積し、中国の経済成長を牽引しました。

経済特区って全部、東側にありますね。だからこっちが発展したのか
西側地域の現状と課題
一方、西側にはチベット自治区や新疆ウイグル自治区などがあり、山岳地帯や砂漠が広がります。交通やインフラの整備が遅れ、産業基盤も弱いため、経済発展のスピードは東側に比べて遅れています。
この地域には少数民族が多く暮らし、文化や生活様式が多様である一方で、経済格差や教育機会の不平等が課題となっています。
絶対的貧困の克服とその限界
生徒たちにこう説明しました。
「中国は2020年、国際貧困ライン(1日2.15ドル未満)で定義される絶対的貧困の撲滅を宣言しました。」
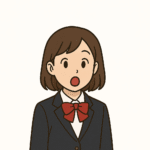
じゃあ、もう貧しい人はいないってことですか?
確かに数字上は貧困層はゼロになりましたが、それは最低限の生活を確保できる水準に達したという意味にすぎません。都市と農村、沿岸と内陸の経済格差は依然として存在し、教育・医療・就業機会の違いは大きく残っているのです。
貧富の格差 ― 都市と農村、沿岸と内陸
ここで、2023年の統計データを示しました。
- 都市部の一人当たり可処分所得は農村部の約2.5倍
- 中国のジニ係数(所得格差指数)は0.47前後で、世界銀行が「格差が大きい」とする0.4を超えている

そんなに差があるんですか…
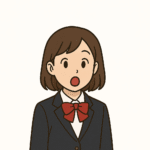
じゃあ、沿岸に住むか内陸に住むかで人生が全然違うってことですね。
その通りです。沿岸部の都市では国際企業や高付加価値産業が集中し、高収入の雇用機会が多いのに対し、内陸部や農村は一次産業や低賃金労働に依存していることが多いのです。
黒河・騰衝線の意味を考えるディスカッション
授業の後半、生徒たちに問いかけました。
「黒河・騰衝線の存在は、これからの中国にとってどんな意味を持つでしょうか?」
活発な議論が展開されました。

西側の発展が遅れているなら、もっと投資やインフラを作るべきだと思います。
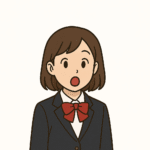
でも、自然条件的に難しいんじゃないですか?

貧しい地域が多いなら、格差はもっと広がるかもしれない。
私はまとめとしてこう話しました。
「この線は単なる地理的な区切りではなく、中国の経済構造・人口分布・社会課題を映す象徴的な存在なのです。」
授業の成果と生徒の変化
身につけた能力
この授業を通じて、生徒たちは以下の能力を身につけました。
統計から背景を読み取る力
人口比率や所得統計を通じて、数字の背後にある歴史・地理・経済の関係を理解する力
比較の視点
自国(日本)と中国を比較し、異なる発展パターンや政策の影響を考察する視点
批判的思考
貧困の「解消」と「格差の是正」は異なる課題であることを理解する思考力
生徒の感想
生徒の感想からも、深い気づきがあったことが分かります。
「人口分布にこんな差があるとは思わなかった」
「沿岸と内陸で生活の質がこんなに違うのは驚き」
「数字だけでなく、その理由を探るのが面白かった」
国際理解教育としての意義
この授業実践には、次のような教育的な効果が期待できます。
地理的思考の育成
地図や統計データから社会現象を読み解く力の養成
多角的視点の獲得
一つの現象を歴史・地理・経済・政治の複合的視点から理解する能力の育成
グローバル・シチズンシップの養成
他国の課題を理解し、自国との比較を通じて世界的視野を広げる姿勢の形成
今後の展望と課題
成果
- 抽象的な概念を具体的な地理的事象で理解させることができた
- 統計データの読み取りと解釈能力が向上した
- 中国社会への理解が深まった
課題
- より多様な資料の活用方法の検討
- 日本の地域格差との比較分析の導入
- 評価方法の体系化
まとめ
黒河・騰衝線は、中国の人口と経済の不均衡を一目で示す象徴的なラインです。沿岸部は鄧小平の改革開放政策の恩恵を受け、国際貿易と産業集積で急速に発展しましたが、内陸部は依然として経済的に遅れをとっています。
絶対的貧困は克服されても、所得格差や地域格差は根強く残り、今後の中国にとって大きな課題となっています。
国際理解教育の場でこのテーマを扱うことは、生徒に「数字の裏にある社会構造」を読み解く力を養い、他国を理解し、自国を相対的に見る視点を育てる上で極めて有効です。そして何より、上海で暮らす生徒たちにとって、自分が立っている場所とその背景を知ることは、世界をより深く理解するための重要な第一歩なのです。


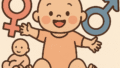

コメント