学習指導要領の位置づけ
高等学校数学A「確率分野」において、学習指導要領(平成30年告示)には次のように記されています。
事象の確率や期待値などを、日常生活や社会の事象に関連付けて理解し、数学的に考察する力を養うこと。
確率や期待値は、教科書の例題だけでは実感が持ちにくい単元です。本実践では、生徒が身近にイメージできる「宝くじ」を題材に、数値に基づいた意思決定の重要性を体感させます。
導入 — 「あなたはこの宝くじを引きますか?」
授業冒頭、黒板に次の問題を提示しました。
「1枚300円の宝くじがあります。当たりは10,000円が1本、ハズレは0円です。全部で10枚しかありません。あなたはこの宝くじを引きますか?」
教室は一気にざわつきます。

10分の1で1万円って、めちゃくちゃお得じゃない?
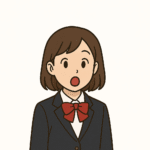
いや、外れたら300円損でしょ!
生徒によって意見が分かれます。実際に挙手を取ると、「買うべき派」と「買わない派」がほぼ半々になることが多いです。
私の回答 — 「買い占めるべき」

私なら、この宝くじは全部買い占めます
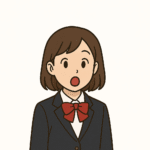
え、なんで先生そんなに自信があるの?
このタイミングで、全10枚を購入した場合の支出と収入を計算させます。
- 全部買うと支出は:300円×10枚=3,000円
- 当たり(1万円)が必ず1枚は手に入るので、収入は:10,000円
- 差し引き:7,000円の利益
つまり、この条件なら100%儲かる「確実に得する宝くじ」であることが分かります。
次の問い — 「いくらまでなら買うべき?」

では、今は買い占めるべきと言いましたが、1枚いくらまでなら買い占めるべきでしょうか?
ここからが本当の狙いです。当たりが1万円なら、支出が当たり金額を超えたら赤字になります。よって、
1枚の価格×10枚<10,000円
を満たす範囲であれば買い占めるべき、という結論に至ります。つまり、1枚1,000円未満なら買い占めは得になります。
このやり取りで、生徒は期待値や損益分岐点の考え方を自然に導き出すことができます。
期待値を導入する
次に、1枚だけ購入する場合の期待値を計算します。
- 当たり確率:\( \frac{1}{10} \)、当たり金額:10,000円
- ハズレ確率:\( \frac{9}{10} \)、当たり金額:0円
期待値E(X) =\( \frac{1}{10} \times 10,000 + \frac{9}{10} \times 0 = 1,000 \) 円
つまり、この宝くじは1枚の平均的な価値が1,000円あるわけです。もし1枚の販売価格が1,000円未満なら「得」、1,000円を超えると「損」ということが見えてきます。
日本の宝くじの具体例:サマージャンボ宝くじで期待値を計算する
公式情報(第1064回 サマージャンボ、1枚300円・1ユニット=1,000万枚)より、当せん金と本数は次の通りです。
- 1等 5億円:各ユニット1本
- 1等の前後賞 各1億円:各ユニット2本
- 1等の組違い賞 10万円:各ユニット99本
- 2等 100万円:各ユニット100本
- 3等 1万円:各ユニット1,000本
- 4等 3,000円:各ユニット100,000本
- 5等 300円:各ユニット1,000,000本
1枚あたりの当せん確率(ユニット1,000万枚を母数として)
- 1等:1/10,000,000
- 1等前後賞:2/10,000,000
- 1等組違い賞:99/10,000,000
- 2等:100/10,000,000
- 3等:1,000/10,000,000 = 0.0001
- 4等:100,000/10,000,000 = 0.01
- 5等:1,000,000/10,000,000 = 0.1
「何かに当たる」確率は上記の合計で約11.01%です。
期待値の計算
各等級の「当せん金×確率」を足し合わせます。
- 1等:5億 \( \times \frac{1}{1,000万} \) = 50.00円
- 前後賞:1億 \( \times \frac{2}{1,000万} \) = 20.00円
- 組違い賞:10万 \( \times \frac{99}{1,000万} \) = 0.99円
- 2等:100万 \( \times \frac{100}{1,000万} \)= 10.00円
- 3等:1万 \( \times \frac{1,000}{1,000万} \) = 1.00円
- 4等:3,000 × \( \times \frac{100,000}{1,000万} \) = 30.00円
- 5等:300 × \( \times \frac{1,000,000}{1,000万} \)= 30.00円
合計:141.99円
1枚300円に対して還元率約47.33%(141.99÷300)になります。
まとめ:サマージャンボ1枚の数学的な平均価値は約142円。長期的には半分弱しか戻らない=夢は大きいが期待値は低い。
参考:宝くじ・スポーツくじ全般の還元率
総務省関連資料によると、宝くじの実効還元率はおおむね45%前後とされています。数字選択式やスクラッチでも大体45〜60%程度で、サマージャンボの期待値とも整合的です。
スポーツくじ(toto/BIG)について
授業では、SNSで話題になった分析として、次のポイントを紹介すると盛り上がります:
- 通常時のスポーツくじの還元率はおおむね約50%。仕組み上、長く買い続けるとプレイヤーは平均で半分程度しか戻らない。
- ただし特殊な回(大量延期・中止試合が発生し、結果が機械抽選になる等)では、売上次第で期待値が跳ね上がることが理論上あり得る。
授業では「プール制×売上×配分率」の関係として紹介すると、確率モデリングの良い題材になります。
発展 — 授業活動
授業では以下の発展活動を行いました。
(1) パラメータを変えて期待値を比較
- 当たり金額、枚数、当選本数を変えて計算
- 還元率や損益分岐点を求める
(2) 現実のギャンブル・くじの分析
- 公営競技(競馬・競艇など)の還元率を調べる
- 宝くじとの違いを議論
(3) 価値観の共有
- 数字で合理的に判断する人
- 娯楽や夢を優先する人
- 双方の立場を尊重しつつ議論する
余談 — 中国の彩票と年齢制限
中国にも「彩票(ツァイピャオ)」と呼ばれる現金が当たるくじがあります。ただし、中国の宝くじは18歳未満は当選金を受け取れないという規定があります。未成年保護や依存症防止の観点は、日本の公営ギャンブルの年齢制限と共通しています。
まとめ
- 期待値は「長期的な平均値」であり、意思決定の根拠になる
- 条件次第では確実に得する宝くじも存在するが、現実の宝くじはほとんどが長期的には損失
- 数学的に損だと分かっても、夢や娯楽の価値をどう評価するかは個人の自由
- 他国の事例(紅包)から、制度や文化の違いも学べる
授業の終わりには、生徒が「先生、この宝くじの条件なら絶対買います!」「でも現実のはやっぱり買わない」と、自分の立場を明確にする姿が見られました。この変化こそ、数字を使って考える力が育った証拠だと感じます。

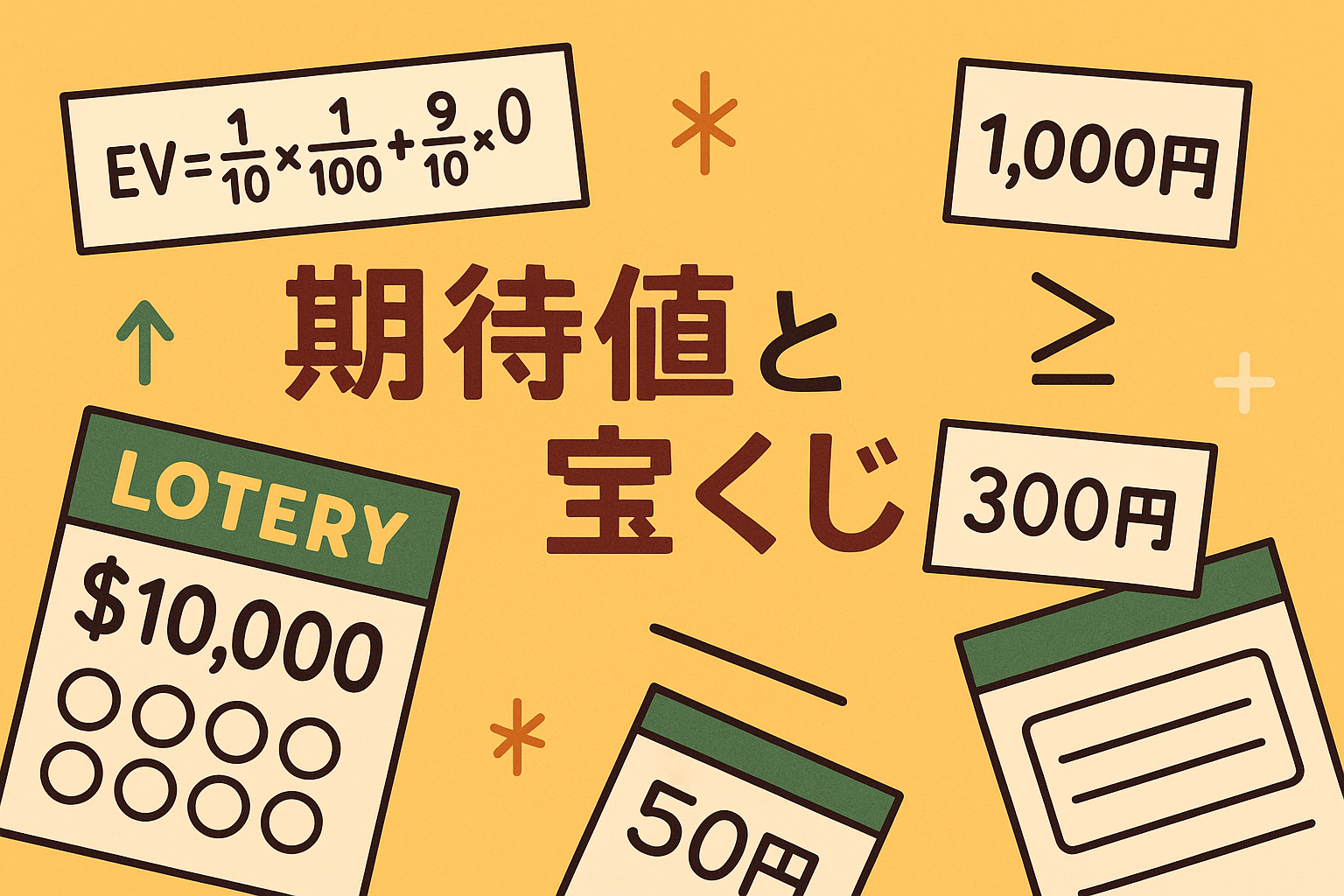

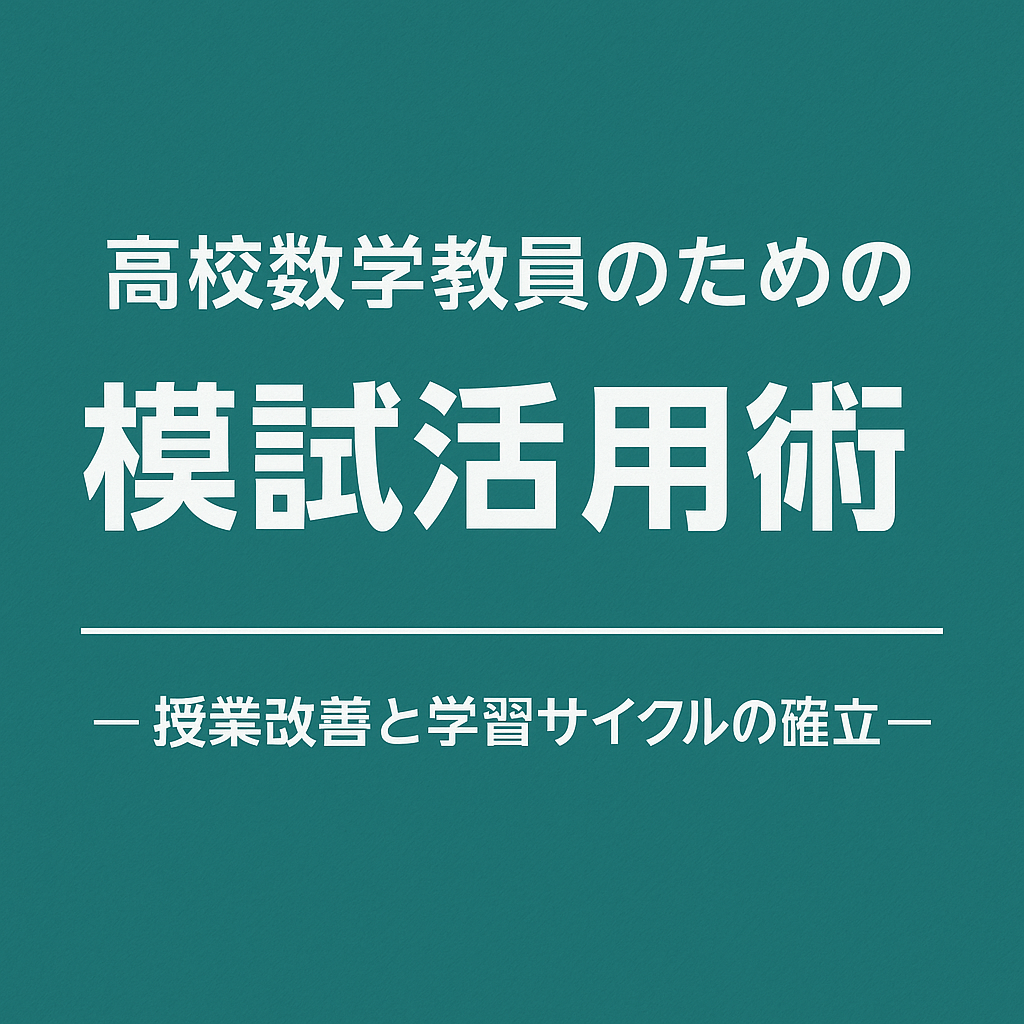
コメント