はじめに
数学Bの「統計的な推測」の分野は、学校によって取り扱い方が異なる場合があります。今回の記事では、2023年度に日本人学校で実施した授業実践をご紹介します。
ここで扱うのはシミュレーションに基づく統計的推論(SBI: Simulation Based Inference)です。SBIは、アメリカでは生徒が統計的・数学的概念をより深く理解するのに効果的な指導法として広く用いられています。本授業は、『シミュレーションに基づく統計的推論とアクティブ・ラーニングの授業事例』(ジミー・ドイ)【論文はこちらから】で紹介されている実践を参考にしました。
題材としたのは、イェール大学で行われ、Nature誌にも掲載された有名な乳児の社会的行動認識実験です。この題材を高校生向けにアレンジし、仮説検定やp値の考え方を体験的に理解させることを目的としました。
数学Bの目標と「統計的な推測」の位置づけ
数学Bの目標として、「学びに向かう力・人間性等」に関わる資質・能力の育成が掲げられています。
数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度、粘り強く柔軟に考え数学的論拠に基づいて判断しようとする態度、問題解決の過程を振り返って考察を深めたり、評価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。
ここで注目すべきは、数学Bでは数学Ⅰの目標に比べて「柔軟に」という表現が加えられている点です。これは、自然対数の定義や広義積分などの厳密な数学的理論に深入りせず、実社会での活用を意識した学習を行う必要があるためと考えられます。
また、高等学校学習指導要領では、統計分野の「統計的な推測」に関して、次のように記されています。
統計的な推測について、数学的活動を通してその有用性を認識するとともに、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 知識及び技能
(ウ)二項分布と正規分布の性質や特徴について理解すること。イ 思考力、判断力、表現力等
(イ)目的に応じて標本調査を設計し、収集したデータを基にコンピュータなどの情報機器を用いて処理するなどして、母集団の特徴や傾向を推測・判断するとともに、標本調査の方法や結果を批判的に考察すること。
授業の流れ
1. 実験の紹介
授業の導入では、研究者が行った乳児実験の映像を視聴しました。ステージ上のキャラクターが山を登る場面を見せ、別のキャラクターが「助ける」場合と「邪魔する」場合を乳児に提示します。その後、どちらのキャラクターを選ぶかを観察するという実験です。
実際の実験では、16人中14人の乳児が「お助けキャラクター」を選びました。
2. 仮説を立てる
ここで生徒たちに問いかけました。
- この結果は、乳児が本当に「お助けキャラクター」を好んでいるからなのか?
- それとも、偶然このような結果になっただけなのか?
仮説としては次の2つを設定しました。
- 帰無仮説:「乳児はどちらのキャラクターも好まない」(ランダムに選んでいる)
- 対立仮説:「乳児はお助けキャラクターを好む」
3. コイン投げによるシミュレーション
手作業シミュレーション
「ランダムに選ぶ」ふるまいを再現するために、公正なコインを用意し、以下のように対応させました。
- 表 = 「お助けキャラクター」
- 裏 = 「お邪魔キャラクター」
16回投げる試行を各生徒が1回ずつ実施し、「表」が出た回数を記録しました。40人分の結果をドットプロットにして可視化しました。
コンピュータシミュレーション
次にJavaアプレットを使い、同じシミュレーションを10万回繰り返しました。その結果、14回以上「表」が出る確率は約0.002(0.2%)であることがわかりました。
生徒たちは、この確率の低さから、実験結果は偶然とは考えにくく、「乳児はお助けキャラクターを好む」という仮説を支持する根拠になると判断しました。
学びのポイント
1. 体験から仮説検定の流れを理解
SBIでは、統計用語を先に教えるのではなく、体験を通して「仮説→データ→検証」という流れを掴ませます。その後に「帰無仮説」「対立仮説」「p値」といった用語を導入すると、生徒はスムーズに理解できます。
2. シミュレーションと理論の接続
シミュレーション結果が二項分布 B(16, 0.5) に近づくことを確認することで、理論と実験の結びつきを体感できます。
3. ランダム性の直感的理解
「偶然起こりにくい」ことを実感し、統計的推論の意義を自分事として捉えられるようになります。
授業の成果と課題
成果
- 生徒は統計的推論のプロセスを数式に頼らず体験的に理解できました
- 抽象的な概念である「p値」を直感的に捉えることができました
- 統計的な考え方が身近な問題解決に役立つことを実感できました
今後の課題
- より多様な実験例への展開
- 理論的背景との効果的な接続方法の検討
- 評価方法の確立
まとめ
この授業を通して、生徒は以下の統計的推論のプロセスを体験的に学びました。
- 仮説を立てる
- 実験やシミュレーションでデータを集める
- 結果から判断する
SBIは、統計教育において「概念の理解」を促す有効なアプローチです。特に高校段階では、このようなアクティブ・ラーニング型の授業が、統計を「使える知識」として定着させる鍵になると考えます。
従来の公式暗記中心の学習から脱却し、体験と思考を重視した統計教育の実践は、生徒の数学的思考力の育成に大きく貢献するものと確信しています。

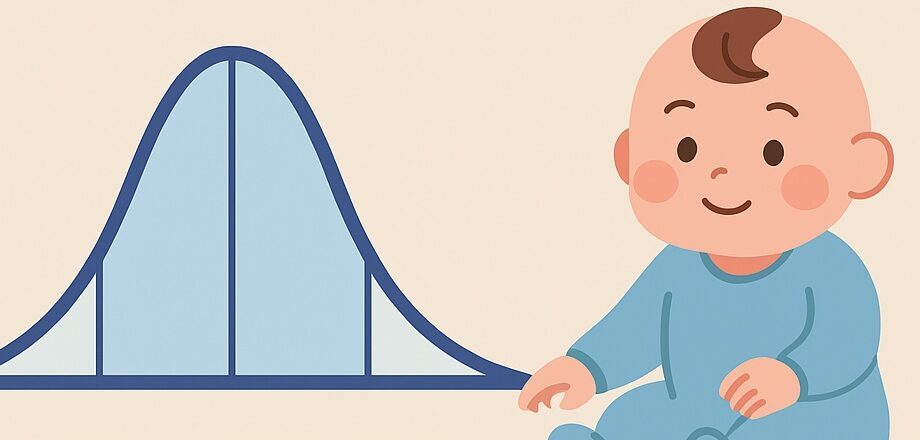
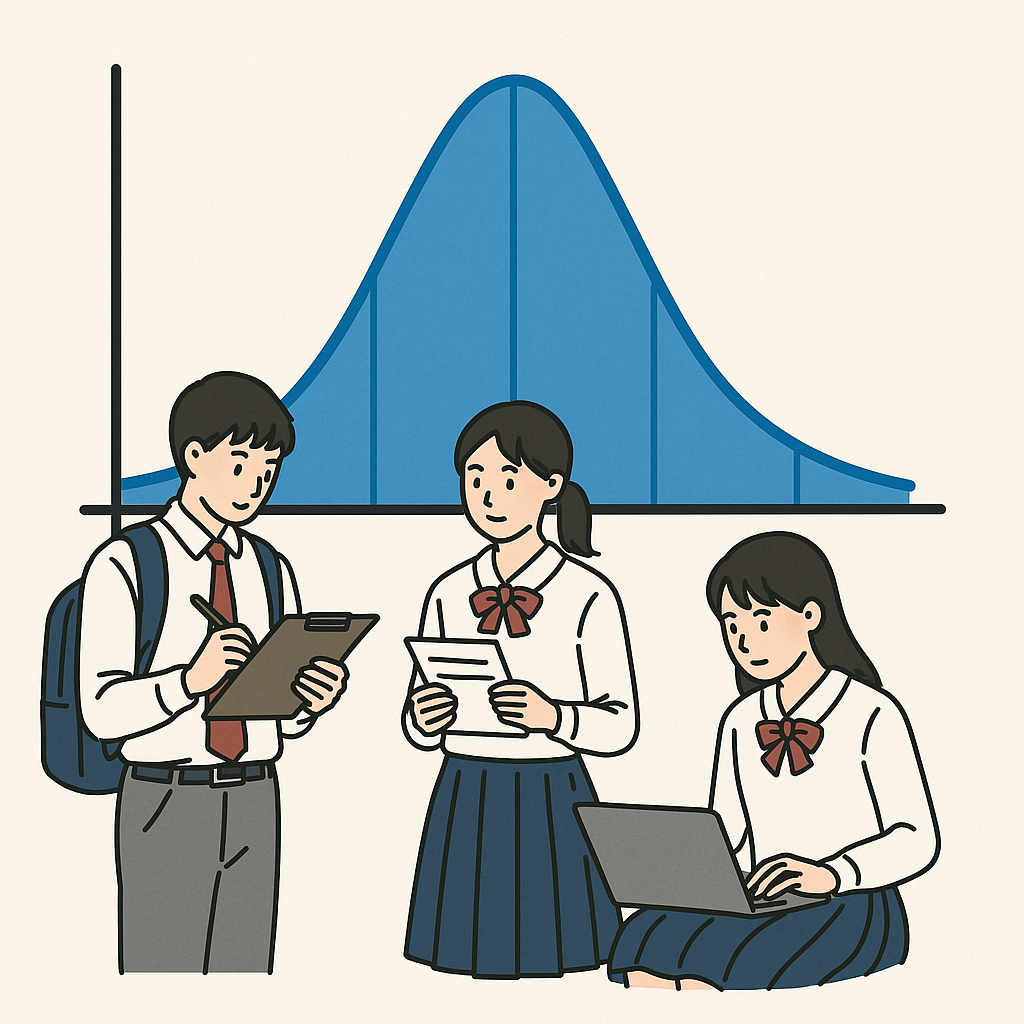
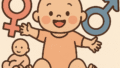
コメント