はじめに
2022年、私は日本人学校に着任しました。当初は、コロナ禍という厳しい状況下での教育活動を強いられましたが、その中でも「今だからこそできること」や「中国だからこそできる学び」にこだわりながら、生徒との対話を大切にした授業づくりに取り組んできました。
この記事では、中国での授業実践や生活、そして創意工夫を凝らして実現した学校行事についてご紹介します。
授業で大切にしていたこと ― 対話から始まる数学的思考
私が授業で最も大切にしていたのは、「対話」です。単に公式を教え込むのではなく、生徒の思考や問いを引き出し、それに基づいて授業を展開していくことを心がけてきました。問いかけから始まり、意見の共有、発表、ふりかえりといったプロセスを通して、数学を“使って考える力”を育むことを目指しました。
また、教科書にとどまらず、数学的活動を積極的に取り入れることも意識しました。例えば「図形の性質」の単元では、三心(重心・内心・外心)が実際の建築物やデザインにどのように活かされているのかを探究する授業を行いました。上海にある建築物を題材に、自ら調べ、考え、発表することで、学びが現実と結びつき、生徒たちの思考もより深まったと感じました。

中国ならではの教材と探究活動
現地の文化や環境を活かした探究活動も、私の教育観を大きく広げてくれました。日本人学校では、中国で活躍する日系企業と連携し、実際の企業が抱える課題についてともに考えるPBL型(課題解決型学習)の取り組みが行われています。
このような活動を通して、生徒たちは現実社会とのつながりを実感しながら、課題に取り組む力を育んでいきました。「学校の学びが、社会とつながっている」という実感を持つことは、生徒の学習意欲を大いに高めるものでした。

コロナ禍でも実現できた、日本人学校らしい行事
着任初年度は、厳格なコロナ対策が続く中での学校生活でした。それでも、「日本人学校らしい行事を何とか実現したい」という思いから、教職員が一丸となって取り組みました。
運動会は、感染拡大防止のために中止となりましたが、登校が再開されたタイミングでクラスマッチを実施。限られた条件の中でも、生徒たちは楽しそうに体を動かし、クラスの団結を深める姿が印象的でした。
また、文化祭は学校内での活動が制限されたため、放課後に校外で撮影した動画を編集し、体育館で全校生徒が鑑賞する形式となりました。誰も経験したことのない新しい形でしたが、生徒たちは企画から編集まで主体的に取り組み、思いのこもった発表が数多く生まれました。
さらに、日系報道機関の協力により、さまざまな著名人からのビデオメッセージが寄せられました。生徒たちは「一人じゃない」と実感し、心が温まる文化祭となりました。
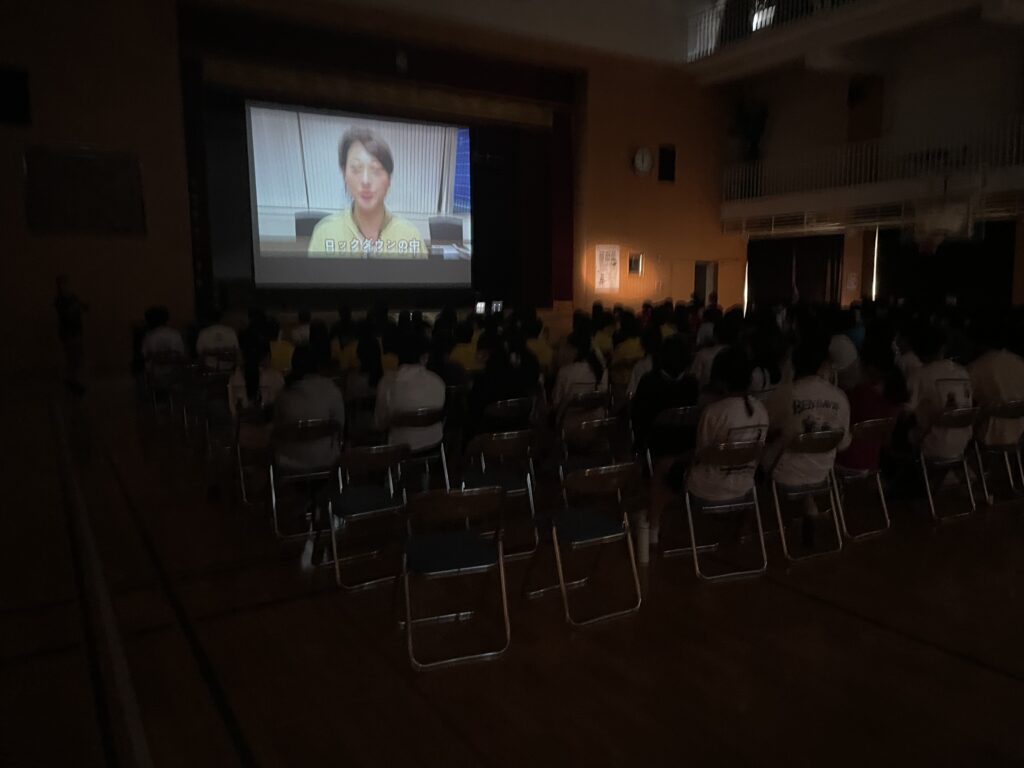
教室の外にも広がる学びと関係づくり
授業以外の時間も、生徒との関係づくりを大切にしていました。放課後や休み時間には雑談や相談を通して生徒の心に寄り添う時間を意識的に持つようにしていました。
登校が再開された後も、毎朝のPCR検査や、突然の小区(居住区)封鎖によって登校できない日が発生するなど、生徒たちは常に不安と隣り合わせの中で生活していました。そうした状況だからこそ、生徒の声に耳を傾けることが、学習以上に大切な支えになると強く感じていました。
また、教員同士のつながりも心の支えとなりました。同じマンションに住んでいた同僚とは、放課後に1階の日本食屋で語り合うこともあり、互いに励まし合いながら乗り越える時間が、精神的な余裕につながっていました。海外での生活を支えるのは、人とのつながりだと改めて実感した日々でした。

おわりに
コロナ禍という特殊な状況下でも、上海日本人学校での授業や学校行事、そして生活は、私にとってかけがえのない経験となりました。制限があるからこそ工夫し、生徒とともに新しい形の教育を築いていく喜びがありました。
しかし、2022年末には中国全体でコロナ対策が一気に緩和され、これまでの厳格なPCR検査や健康コードの制度が突然廃止されました。その直後、感染が爆発的に拡大し、学校現場にも大きな影響を与えました。
次回の記事では、コロナ対策が終わった直後の混乱の様子や、学校としてどのように対応したのか、生徒や教職員の間でどんな変化があったのかについて詳しく振り返りたいと思います。感染の波の中でも、学びを止めず、どう支え合いながら教育を続けていったのか、その過程を綴っていきます。



コメント