はじめに
2022年8月、ようやく私は赴任地に到着しました。しかし、当時の赴任地ではまだ厳格なコロナ対策が続いており、到着してすぐに学校で勤務を始めることはできませんでした。本記事では、中国での生活が始まった直後の様子や、生徒たちの登校再開、そしてコロナ禍での教育活動について振り返ります。
高鉄で移動——異国の広さを実感
到着した地での隔離期間を終えた後、学校が手配した車で駅へ向かい、中国の新幹線「高鉄」で上海へ移動しました。およそ6時間の列車の旅では、中国の広大な大地や街の風景が次々と車窓に流れ、異国にいることを改めて実感しました。
赴任地の駅に到着後も、学校手配の車でそのまま住居となるマンションへ。渡航・隔離を共にした同僚とは、同じ建物の9階と10階に割り当てられ、不安もある中で心強さを感じました。初日の夜には、マンション1階の日本食屋さんで飲んだビールが、何とも言えない安心感をもたらしてくれました。今思い出しても、最高の一杯です。

到着後の手続きラッシュ
到着2日目には、労働ビザの正式取得に向けて、指定医療機関での体格検査や、携帯電話の契約を行いました。すべて中国語での対応となるため、事務員さんのサポートには本当に助けられました。
続けて、銀行口座の開設や、健康コード(健康碼)の登録、労働ビザの最終取得などの手続きを順に進めました。特に、銀行口座は中国での電子決済(WeChat PayやAlipay)利用に不可欠で、現金をほとんど使わない生活がスタートしました。
到着後も学校に入れない1週間
しかし、到着後すぐに学校で働けたわけではありません。当時の中国では、他都市からの移動者は学校のような大勢が集まる施設に1週間入れないという規定がありました。そのため、自宅待機をしながら、引き続きオンラインで業務を行う日々が続きました。
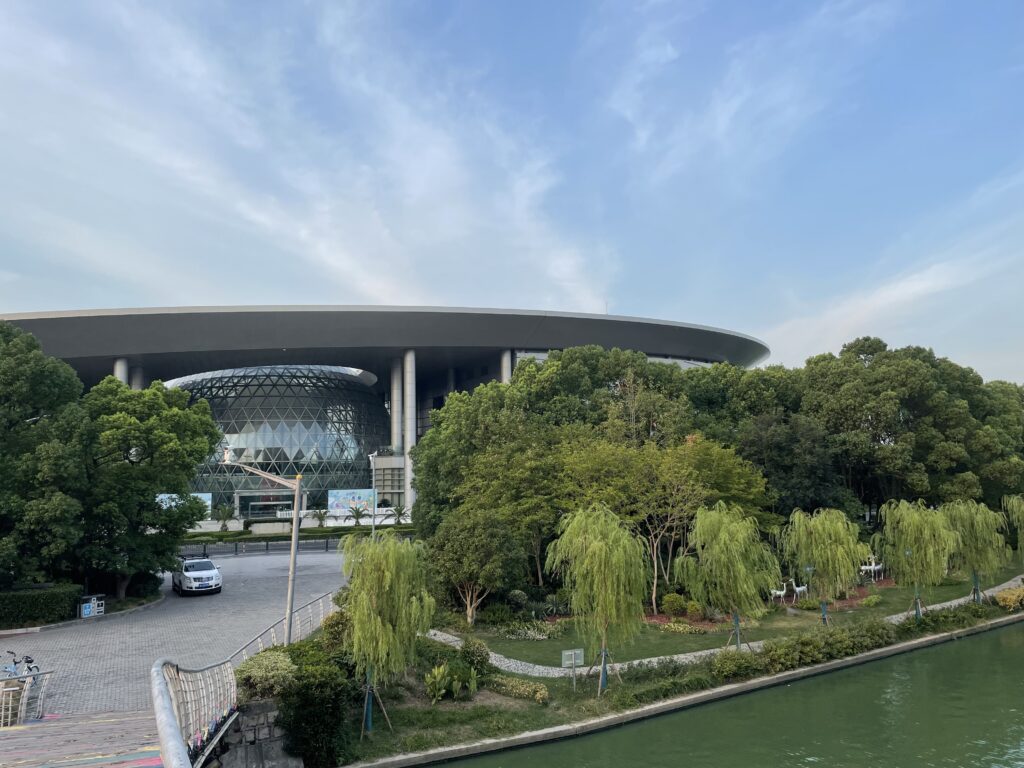
厳格なコロナ対策
2022年当時の上海は、日常のあらゆる場面でコロナ対策が求められました。外出先では必ず健康コードをスキャンし、定期的なPCR検査も義務づけられていました。これを怠ると、スーパーや交通機関の利用も制限されるほどの厳しさでした。
日々の生活には不便もありましたが、一方でその徹底ぶりに驚かされることも多く、「今、この場所で自分が働こうとしているのだ」という覚悟にもつながりました。
ようやく始まった対面授業
待機期間を終え、ようやく学校に足を踏み入れられたときの嬉しさは、今でも忘れられません。同時に、生徒たちも登校を再開しました。長く続いたオンライン授業を経ての再会は、私にとっても、生徒たちにとっても新鮮で、どこか照れくささを感じながらのスタートでした。
対面授業では、オンラインでは伝えきれなかった表情や反応を見ながら指導できるようになり、より深い理解へとつながっている実感がありました。グループワークやちょっとした雑談ができるのも、対面ならではの喜びです。
コロナ禍の中での学校生活
とはいえ、コロナ禍はまだ終わっていませんでした。学校内でもマスク着用や手指消毒は当然のこと、定期的なPCR検査の実施、もしもの際にはすぐオンラインに戻れる体制も整えられていました。
生徒たちの中には、長い自宅待機でストレスを感じている様子も見られました。そうした様子に気づけるのも、対面だからこそ。授業中に雑談の時間を設けたり、授業外での相談に応じたりと、精神的なサポートも意識して関わるようにしていました。
おわりに
到着からの1週間は、手続きや待機であっという間に過ぎていきましたが、いよいよ始まった対面授業では、生徒たちとのリアルなやりとりに教育の楽しさを改めて感じました。
次回の記事では、実際の授業の工夫や行事、そして上海での生活がどう広がっていったかについて、さらに詳しく紹介していきます。




コメント