近年、高等学校教育において「探究」は欠かすことのできない概念となっています。「総合的な探究の時間」の必修化をきっかけに、多くの学校で探究的な学びが導入されていますが、その一方で、「探究が形式化してしまっている」「教科の学習と切り離されている」といった課題も指摘されています。
本記事では、私が高2の担任として、37名の生徒に年間2本の3000字論文を書かせる探究実践を行った経験をもとに、探究を以下の4つの視点から捉え直し、その意義を考えてみたいと思います。
- 学年としての設計
- 担任としての個別伴走
- 進路・キャリア指導
- 各教科での日常的な学び
探究を支える学年としての設計
本学年の探究は、学年主任を中心とした丁寧な設計から始まりました。4月から5月にかけて、まず「論文とは何か」「探究とはどのような学びなのか」といった基礎的な内容について、学年全体で共通理解を図りました。探究を感覚的な活動として始めるのではなく、学術的な文章の構造や、問いを立てて考察するという研究の基本型を押さえた上でスタートできたことは、大きな意味があったと考えています。
続いて6月に行われた研究デザインシートの作成では、「なぜそのテーマを扱うのか」「何を明らかにしたいのか」「どのような方法で考えるのか」を明文化しました。これは、探究を思いつきや興味本位で終わらせず、思考の道筋を可視化するための重要なプロセスでした。この段階で、テーマが漠然としすぎて問いが立てられない生徒や、逆に問いが狭すぎて論じる余地がない生徒も見られ、個別の対話が必要となりました。
さらに、7月に設けられた高3生の中間発表を聞く機会は、探究のイメージを具体化する上で非常に効果的でした。先輩たちが自分の言葉で探究を語る姿は、高2生にとって現実的な到達目標となり、「来年の自分」を想像する材料になったように思います。
加えて、大学院で教育学を専門とする講師の方から研究内容について話を伺う機会もありました。研究とは特別な存在だけが行うものではなく、身近な疑問を問いとして深めていく営みであることを、生徒は具体的な実例を通して理解できたのではないでしょうか。
高2担任として取り組んだ「3000字論文×年間2本」
担任としての探究指導の柱は、3000字論文を年間2本書かせるという取り組みでした。3000字という分量は、生徒にとって決して小さな負荷ではありません。しかし、この分量は単なる量的課題ではなく、思考を途中で止めないための装置として設定しました。
問いを立て、背景を整理し、資料を踏まえて主張を構築し、結論へとまとめる。この一連の思考過程を言語化するためには、一定以上の分量が必要です。1本目(10月提出)では多くの生徒が構成や論理展開に苦労しました。特に、「問いに対する答え」と「自分の感想」の区別がつかない、引用と自分の主張が混在する、といった課題が目立ちました。
しかし、2本目(2月提出)に向かう過程では、問いの立て方が「〜はどうか?」という単純なものから「なぜ〜なのか、その背景には何があるのか」という多層的なものへと変化し、段落構成にも明確な成長が見られました。探究は一度きりではなく、繰り返しの中でこそ育つ学びだと実感しています。
昼休みの定期面談による「伴走型」の支援
担任として特に意識していたのが、昼休みを活用した定期面談です。毎日1人、10分程度という短い時間ではありますが、37名全員と月に1〜2回のペースで継続的に対話することで、生徒一人ひとりの思考の変化や悩みを把握することができました。
面談では、学習状況や生活面に加え、探究についても必ず触れるようにしていました。「今どんな問いで悩んでいるか」「一番書きにくいのはどこか」「自分の主張は何だと思うか」といった問いを投げかけ、生徒自身が考えを言葉にする時間を大切にしました。
ここで重視していたのは、答えを与え過ぎないことです。担任の役割は、結論を示すことではなく、生徒が自分の問いと向き合い続けられるよう支えることだと考えています。短い面談でも、問い返しを行うだけで、生徒の思考が一段深まる場面が多く見られました。
ただし、すべての生徒がこの面談を肯定的に受け止めていたわけではありません。中には「忙しい昼休みを使われるのが負担」という声もあり、面談の意義を丁寧に説明する必要性を感じる場面もありました。
探究と進路・キャリアを結び付ける指導
探究を探究だけで終わらせないために、LHRの時間を活用し、進路やキャリアと意識的に結び付けた指導を行ってきました。11月の大学調べでは、偏差値や入試方式だけでなく、「その大学・学部では何を学ぶのか」「どのような研究が行われているのか」に注目させました。
また、12月から1月にかけての仮の志望理由書の作成・添削を通して、「なぜその分野に興味を持ったのか」「その関心は探究テーマとどうつながっているのか」を問い返しました。探究で考えてきたことが、将来の学びや進路選択と地続きであることを、生徒自身が実感できるようにするためです。実際、探究テーマと志望理由が自然に結びついた生徒は、志望理由書の説得力が格段に増していました。
テーマ設定においては、部活動や日常の興味・関心も重視しました。面談や日常の会話を通して、「何に時間を使っているのか」「どんな話題のときに表情が変わるのか」を丁寧に観察し、それを探究テーマへとつなげていきました。
教科の学びそのものが探究的であるという環境
今回の実践を振り返って、改めて「恵まれた環境だ」と感じた点があります。それは、教科の学習そのものが探究的な活動を多く含んでいるということです。
例えば、政治経済の授業では、仮想的に株式投資を行う活動が取り入れられており、生徒は経済の仕組みを「知識」として学ぶだけでなく、意思決定やリスクについて体験的に考える機会を得ています。また、文学総合では、文学作品を題材に考察論文を作成する活動が行われており、自分の読みを言語化し、根拠をもって主張する経験を積んでいます。
このように、各教科でアウトプットを前提とした学習が行われていることは、探究的な思考を育てる土台を確実に形づくっていると捉えています。日常的に「考え、書き、表現する」経験を積んでいるからこそ、総合的な探究の時間においても、生徒は比較的スムーズに自分の問いと向き合うことができていたのではないでしょうか。
探究は特別な活動ではない
これらの実践を通して強く感じたのは、探究は特別な時間や特別な授業の中だけで行われるものではない、ということです。教科の学習、進路指導、面談、論文執筆といった日常的な教育活動が有機的につながったとき、探究は自然と学校生活の中に根付いていきます。
探究とは、「自分は何に関心があるのか」「なぜそれが気になるのか」「それをどう深めていくのか」と問い続ける営みです。その問いに向き合う過程そのものが、生徒の将来を支える力になっていくのだと思います。
担任として、生徒一人ひとりの進路や将来像を意識しながら探究に関わることができたことは、私自身にとっても大きな学びでした。課題や困難もありましたが、今年度の実践は、探究が学校全体の文化として育っていく可能性を感じさせてくれるものであったと考えています。
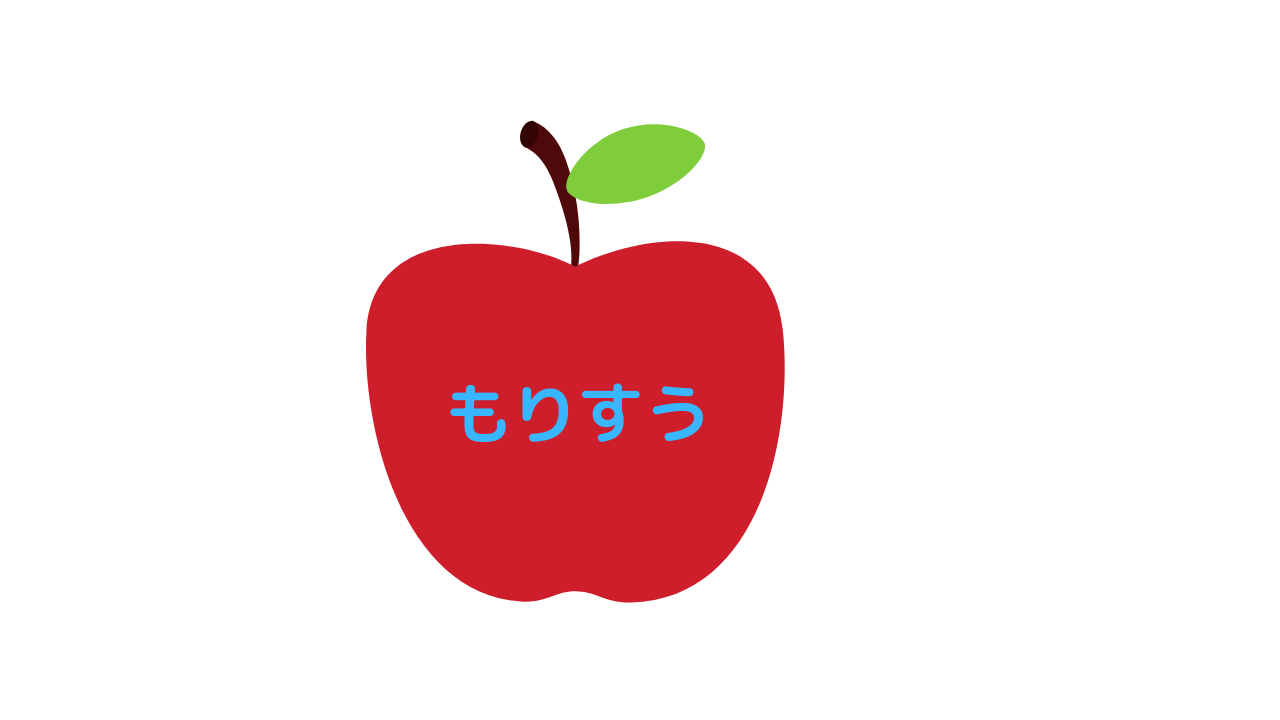



コメント