はじめに ― 生成AIへの違和感から出発する
生成AI(Generative AI)が教育現場に入り込み始めてから、「教育はどう変わるのか」「生成AIをどう活用すべきか」という議論が盛んに行われています。
しかし、現場の教員として率直に感じるのは、生成AIを使うことで、生徒の能力は本当に育っているのかという違和感です。
そもそも、既存の教育がどれほど確実に能力を開発できてきたのかは分かりません。また、これまで育ててきたとされる能力が、これからの社会で本当に役に立つのかも、誰にも保証できません。
本記事では、生成AIを無条件に肯定するのでも、全面的に否定するのでもなく、教育はもともと不確かな営みであるという前提に立ったうえで、生成AIによって教育は何を失い、何がより鮮明になるのかを考えます。
そして最後に、数学教育がこの時代に果たし得る役割を整理します。
世界的に進む「生成AI前提社会」という現実
生成AIは、すでに一部の専門家や大人だけのものではありません。世界的に見ても、生成AIは「使うかどうかを選ぶ対象」ではなく、存在を前提に向き合わざるを得ない環境条件になりつつあります。
アメリカでは、ニューヨーク市教育局が、生成AIを一律に禁止するのではなく、AIの出力を批判的に吟味する力を育てる方向へと舵を切りました。
また、Googleが提供する生成AI「Gemini」は、保護者の管理や同意を前提に、13歳以上の利用を想定した設計を進めています。これは、中高生が生成AIを使うことを、社会が前提として受け入れ始めていることを示しています。
日本でも、文部科学省が、生成AIを一律に排除するのではなく、目的と注意点を明確にした上で慎重に扱うという立場を示しています。
世界的に見れば、「生成AIを教育で使うかどうか」という問い自体が、すでに時代遅れになりつつあると言えるでしょう。
教育の目的と生成AIの緊張関係
しかし、社会的に前提化が進んでいるからといって、それが教育的に望ましいとは限りません。
教育の目的は、成果物を整えることではなく、生徒自身の能力を開発することにあります。
能力が育つ過程には、本来、次のようなプロセスが不可欠です。
- わからない
- 試行錯誤する
- 間違える
- 修正する
このプロセスには、時間と負荷が伴います。
生成AIは、このプロセスを大幅に省略し、最初から「それらしい完成形」を提示します。その結果、生徒は「できたような気分」になりやすい一方で、生徒の中に何が残ったのかは極めて曖昧になります。
この意味で、生成AIは能力開発と本質的に緊張関係にあります。
教育の不確かさという前提
ただし、ここで一つ立ち止まる必要があります。
それは、生成AI以前の教育が、どれほど確実に能力を開発できていたのかは分からない、という事実です。
学校教育では長年、次のような力を育ててきたとされてきました。
- 思考力
- 判断力
- 表現力
しかし、それらがどの程度身につき、どのような場面で発揮されているのかを、私たちは正確に測定できているわけではありません。
さらに言えば、学校で育ててきた能力が、これからの社会で本当に役に立つのかどうかについても、確かな保証はありません。
教育とはもともと、結果が保証された営みではないのです。
生成AIは、教育の不確かさを露わにする存在である
生成AIの登場によって、「考えたつもり」「分かったつもり」「できたつもり」は、これまで以上に簡単に生み出せるようになりました。
しかしそれは同時に、教育がどこまで生徒の能力を育てられていたのか、という問いを、より露骨な形で突きつけます。
生成AIは教育を壊す存在というよりも、教育の曖昧さや弱さを、はっきりと可視化する存在だと言えるでしょう。
それでも数学教育が持つ意味
このような時代において、数学教育の価値はむしろ鮮明になります。
数学の世界では、最終的に問われるのは「正しそうかどうか」ではなく、その主張が真か偽かです。
- 条件は満たされているか
- 論理に飛躍はないか
- 反例は存在しないか
曖昧なまま終わることは許されません。最終的には、真偽のいずれかを引き受ける必要があります。
生成AIは、もっともらしい説明や論理を提示することは得意です。しかし、その内容が真であるかどうかを保証することはできません。
たとえば、直線束を扱った授業で、生成AIに「2つの直線の交点を通る直線の集合を図示してほしい」と依頼したことがあります。AIは瞬時にグラフを生成しましたが、よく見ると不動点を正確に通っていないように見えます。生徒たちは「不動点を通っていないよね」と気づき、修正を指示しました。しかし再び不正確な図が出てくる。
ある生徒は「先生の説明と同じことを言っているね」と検証し、別の生徒は「でも図が間違っているよね」とグラフの精度に疑問を持ちました。この一連のやりとりの中で、生徒たちは生成AIが「もっともらしく答える存在」であっても、「真偽を保証する存在ではない」ことを体感的に理解していきました。
だからこそ数学教育は、生成AIの出力を信じる側ではなく、真偽を判断する側に立つ経験を積ませる教科として、極めて重要な役割を果たします。
生成AIを「使いこなす」とは何か
生成AIを使いこなすとは、うまく質問できることでも、早く答えを得ることでもありません。
それは、生成AIの出力が真か偽かを、自分で判断できる立場に立つことです。
数学教育で培われる、次のような力は、そのまま生成AI時代のリテラシーになります。
- 定義を厳密に読む力
- 条件を落とさない力
- 論理を最後まで検証する姿勢
こうした力は、実際の授業の中でどのように働くのでしょうか。
先ほどの直線束の授業では、生成AIが提示したグラフに対して、生徒たちは「本当に不動点を通っているか」を自ら確かめようとしました。ここで働いているのは、まさに「条件を落とさない力」であり、「論理を最後まで検証する姿勢」です。生成AIの出力を「それらしい」と受け入れるのではなく、「本当に条件を満たしているか」を問い直す。この経験こそが、生成AIを使いこなす基盤になります。
おわりに ― 真偽を引き受ける教育へ
生成AIによって、教育は「良くなる」「悪くなる」というよりも、教育の本質がより厳しく問われるようになるのだと思います。
能力が本当に育っているのか、その能力は将来役に立つのか。これらの問いに、確かな答えはありません。
それでも教育が続けられるとすれば、それは、不確かな世界においても、真偽を引き受け、考え続ける姿勢を育てるためではないでしょうか。
数学教育は、真偽を引き受ける経験を積ませる教科として、生成AI時代において、これまで以上に重要になると考えています。
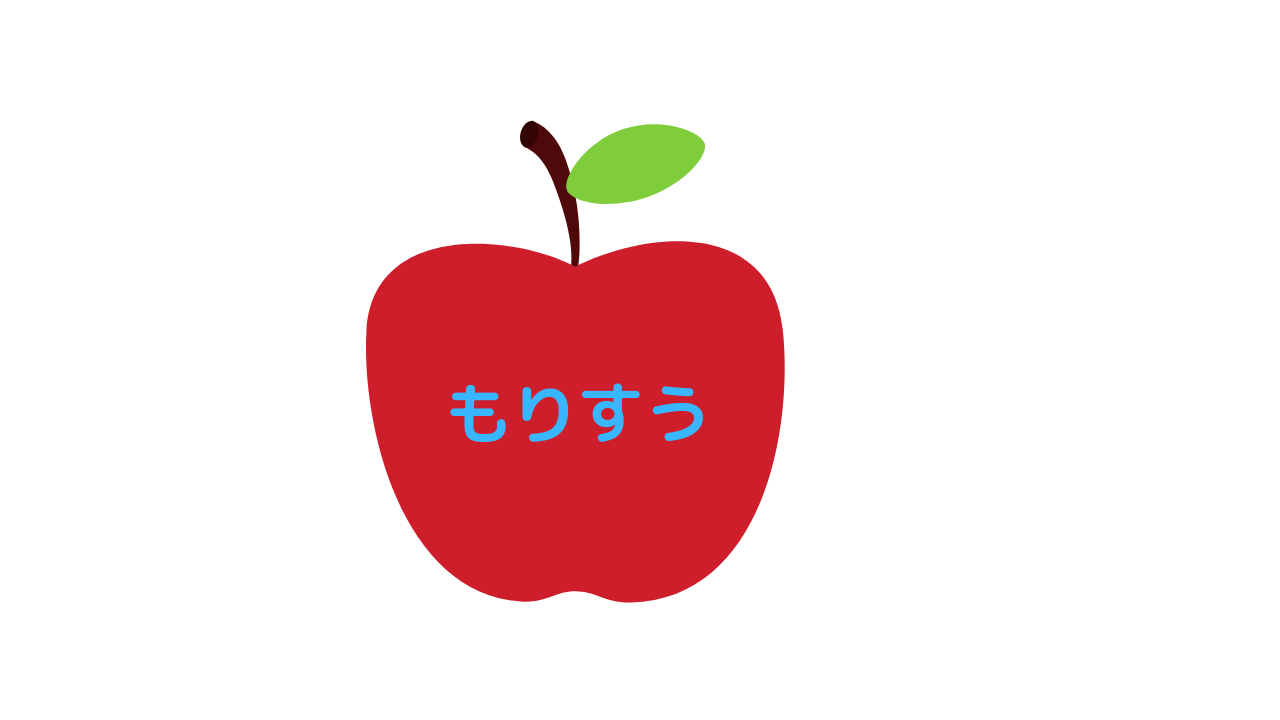



コメント