はじめに
2023年度の「総合的な探究の時間」の10月から12月の間に、1・2年生あわせて約100名の生徒が、教員が提示した15の探究テーマの中から自ら選び、8人までの少人数のグループに分かれて約8週間のテーマ別探究に取り組みました。
私はそのうちの1講座、「美味しいコーヒーの淹れ方」を担当しました。テーマ設定の意図は、身近な日常生活の中にある“あたりまえ”を問い直し、観察・仮説・検証を通じて、自分なりの答えを導く力を育むことにありました。
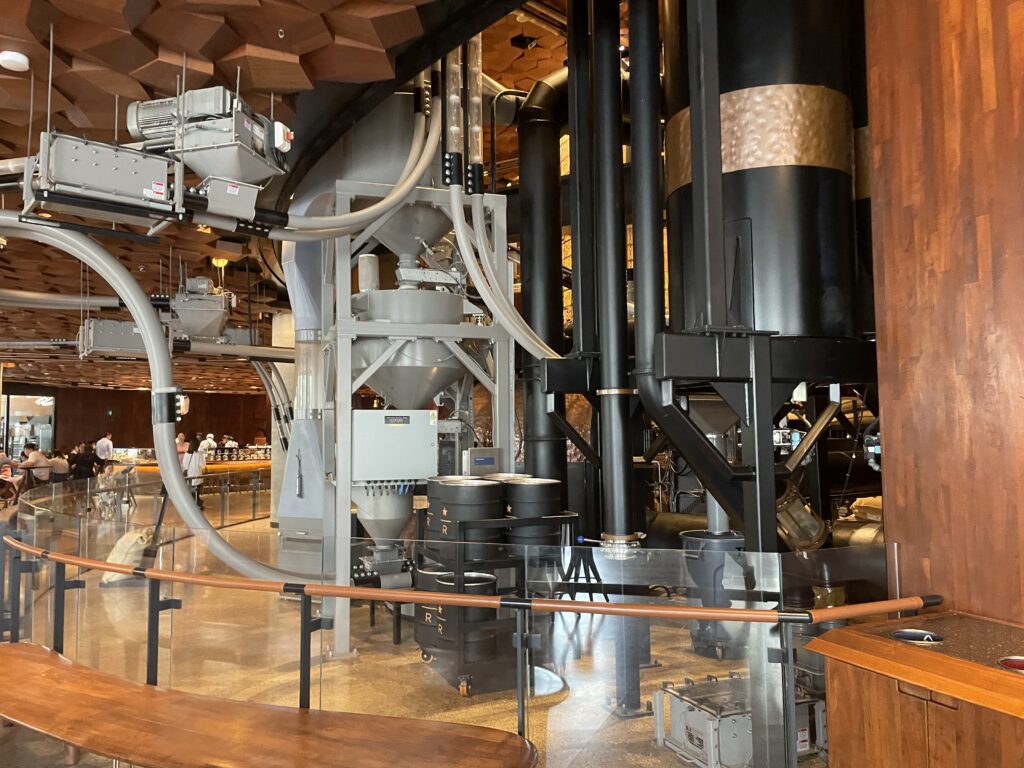
講座の構成と探究の流れ
この探究講座は以下のような8週構成で進め、生徒たちが自ら問いを立て、考え、実験し、振り返るプロセスを体験できるよう設計しました。
■ 第1〜3週:情報収集と問いの形
生徒たちは最初の3回で、インターネット・書籍・動画などを活用しながら、「美味しいコーヒー」とは何か、自分たちにとっての「美味しさ」とは何かについて調べ、話し合いました。調べていく中で、「コーヒー豆の産地について」「抽出道具・方法」「焙煎度」「お湯の温度」「抽出時間」など、味を左右する多くの要素に気づき、それぞれのグループが探究テーマを絞り込んでいきました。

■ 第4週:グループ内発表と仮説の共有
各自が調べた内容をグループ内で発表し、意見を出し合いながら「どのような条件で淹れれば、自分たちが思う“美味しい”が実現できるのか」という仮説を立てました。
「苦味を抑えるには?」「香りを引き出すには?」「温度はどこまで影響するのか?」といった問いが生まれました。
■ 第5〜7週:実践と検証(実習)
家庭科室を使用し、各グループが実際にコーヒーを淹れて検証する実習を行いました。初回の実習では、まず一般的に「美味しい」とされる基本の抽出方法を実践しました。しかしその結果、生徒たちからは「コーヒーがこんなに苦いと思わなかった」「ミルクを入れたい」といった率直な感想が多数聞かれました。
こうした反応から、「美味しさ」は技術的な正解だけでなく、飲む人の好みによって左右されることを生徒たちは実感していきました。そこで、各グループは「自分たちの“美味しい”を追求するにはどうすればよいか」を再考し、抽出条件(豆の量、湯温、蒸らし時間、挽き方など)を調整しながら試行錯誤を重ねました。
さらに、味の評価に主観が入りやすいことを考慮し、グルーム外の生徒や教員に試飲を依頼していました。そこから集まった多様な意見を分析し、「コーヒーをあまり飲まない人向け」や「コーヒーをよく飲む人向け」などと飲み人を想定した考察を深め、最終的なレシピや淹れ方を工夫していきました。

■ 第8週:発表会(他グルームとの合同)
最終週は、他のテーマのグループも交えての成果発表会を実施しました。探究のプロセス・工夫した点・学んだこと・今後の課題などをまとめてプレゼンテーションを行いました。
生徒たちは、「味の違いに気づけるようになった」「抽出条件でここまで変わるとは思わなかった」「やっぱりコーヒーはあんまり好きじゃない」といった振り返りを口にし、確かな学びを実感していました。
生徒の学びと気づき
この講座では、「正解のない問い」に挑戦しながら、科学的視点・感覚的評価・他者との対話を通じて学びを深めていく姿が見られました。
「焙煎度と粒度、温度について苦味の感じ方が異なる」という結果にたどり着き、3つの組み合わせの記録を毎回細かくとって検証していました。また、「美味しさは個人差がある」と気づき、飲み手を変えて複数の感想を収集し、「それぞれの味覚の好み」に近づけようと工夫を凝らしていました。

終わりに
この講座は、教科横断的な学びや実社会との接続を意識した「探究の実践」として、小規模ながらも生徒にとって意味のある体験となりました。「調べる・考える・試す・伝える」という探究の基本を体感しながら、自分たちで仮説を立て、行動に移し、結果を評価するという学習の楽しさを実感できた講座になったと感じています。
翌年の2024度からは、探究・国際理解教育の主任として、こうした個別講座の経験をカリキュラム全体に還元できるよう、より体系的な探究の構築に挑むことになります。
生徒の「問いたい」「試したい」という思いを育てる場づくりを、今後も模索していきたいと思います。




コメント