はじめに
模試は、単なる「学力測定のイベント」ではありません。模試の最大の意義は、生徒が①準備 → ②本番 → ③復習の学習サイクルを確立し、定期的に学びを振り返る機会を提供することです。さらに、模試や入試の過去問を事前に分析して授業に反映し、結果をもとに授業のアプローチを柔軟に変更することが重要です。場合によっては、高校・中学入試の出題設計に活かし、苦手分野をあえて出題することで、入学後の学びを促すことも可能です。
この記事では、筆者の実践をもとに、模試を授業改善と学校全体の学力向上につなげる方法を体系的に紹介します。
模試の3段階サイクルを生徒に定着させる
準備
模試の前に「準備期間」をしっかり設定し、直前の付け焼き刃的な学習ではなく計画的な学習を促します。具体的には以下のような取り組みを行います。
- 2〜3週間前に範囲表と過去問を提示
- 出題可能性の高い分野を「重点復習リスト」として配布
- 目標点・目標偏差値を生徒自身に設定させる
この段階で重要なのは、模試を「ただ受ける」ものではなく、「自分の成長を測る場」として準備する習慣をつけさせることです。
本番
本番の模試は、単なるテストではなく、時間配分・解答順・見直し方法を実践する訓練の場と位置づけます。授業では次のような戦略を事前に練習させます。
- 「最初の10分で全体を見渡す」
- 「得点しやすい問題から解く」
- 「残り5分は計算チェック」
これにより、模試を入試本番の予行演習として最大限活用できます。
復習
模試後は必ず復習期間を設けます。復習の核となるのは「間違い直しノート」の徹底活用です。
- 間違えた問題を、なぜ間違えたのかで分類(計算ミス/知識不足/思考プロセスの問題)
- 正しい解法を記録し、類題演習を追加
- 1〜2週間後に再テストして定着を確認
この「準備→本番→復習」のループを繰り返すことで、生徒は自然とPDCAサイクルに基づいた学習習慣を身につけます。
模試・入試過去問を分析し、授業で先回りする
数学では「頻出パターン」を押さえることが得点力向上の近道です。模試や入試の過去問を分析し、授業の中で次のような先回り指導を行います。
- ベクトルの大問で「内分点・外分点→三角比活用」という流れが多い場合、該当単元の授業で過去問を一部アレンジして導入
- 二次関数と図形の融合問題が頻出の年度は、授業中から「模試で出やすい解法パターン」を意識させる
- 模試の難問はそのまま解かせるのではなく、易しく改題して導入し、授業で段階的に難易度を上げる
こうすることで、模試当日に「見たことのある形式」の問題に出会える確率が高まり、生徒の心理的負担が軽減されます。
模試結果を受けて授業アプローチを変える
模試は、生徒の現時点での到達度を測る貴重なフィードバック源です。結果を踏まえて授業のアプローチを変えることで、指導の精度が向上します。
短期的対応
- 模試で正答率が著しく低かった単元は、次回授業で10分の補強ミニ講義を実施
- 類題演習を小テスト形式で配布し、解き直しを促進
中期的対応
- 正答率データを活用し、次回定期試験の出題比率を調整
- 学年全体で情報共有し、弱点単元を補習や課題に反映
長期的対応
- 年間カリキュラムの見直し
- 翌年度の授業順序や演習量配分への反映
こうした柔軟な授業改善により、生徒の「現在の状況」に即した指導が可能になります。
入試設計での模試活用
高校入試や中学入試を設計する立場であれば、模試分析は出題方針の策定にも活用できます。特に、学校として強化したい分野や、入学後につまずきやすい単元をあえて入試問題に組み込むことは効果的です。
- 目的:入学後の学びをスムーズにするため、苦手分野を早期に顕在化
- 例:関数と図形の融合問題、場合の数と確率の思考力問題など
- 効果:入学後の指導計画への具体的な反映が可能
これは「選抜」と「教育」をつなぐ視点での模試活用と言えます。
ICTとデータ活用
現代の模試活用には、ICTツールの導入が不可欠です。
- ExcelやGoogleスプレッドシートによる自動集計と弱点単元の色分け表示
- LMS(Google Classroom等)での弱点別課題配信
- オンライン模試解析ツールによる時間配分や思考プロセスの可視化
これにより、生徒・教員ともに分析時間を大幅に削減し、改善行動により多くの時間を割けるようになります。
まとめ
模試の真の価値は、以下の4点にあります。
- 生徒に「準備→本番→復習」の学習サイクルを根付かせること
- 模試や入試の傾向を分析し、授業で先回りすること
- 結果をもとに授業アプローチを柔軟に変更すること
- 入試問題設計にも反映し、入学後の学びを見据えること
模試を「測定」だけで終わらせず、「改善」の起点として活用することで、生徒の学びは飛躍的に向上します。高校数学教員として、このサイクルを意識的に設計することが、授業の質を高める重要な鍵となります。

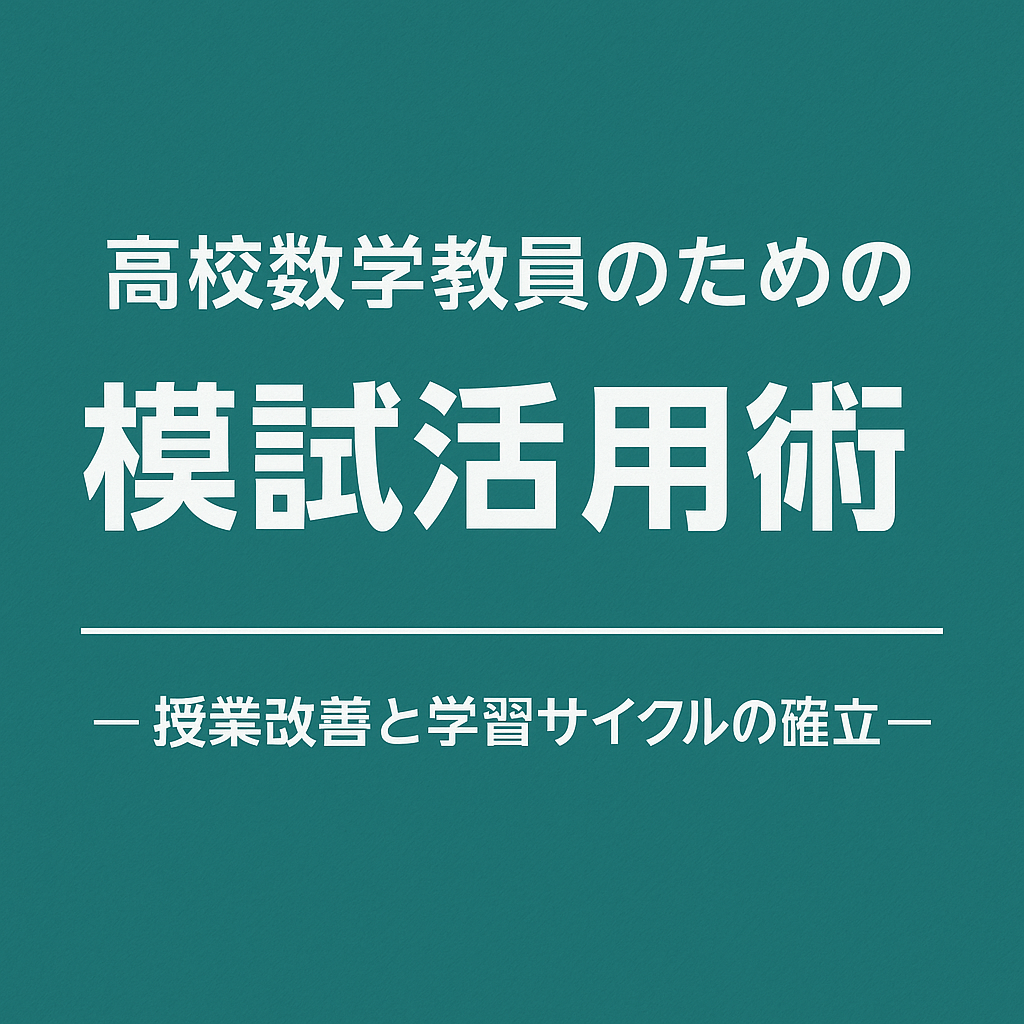
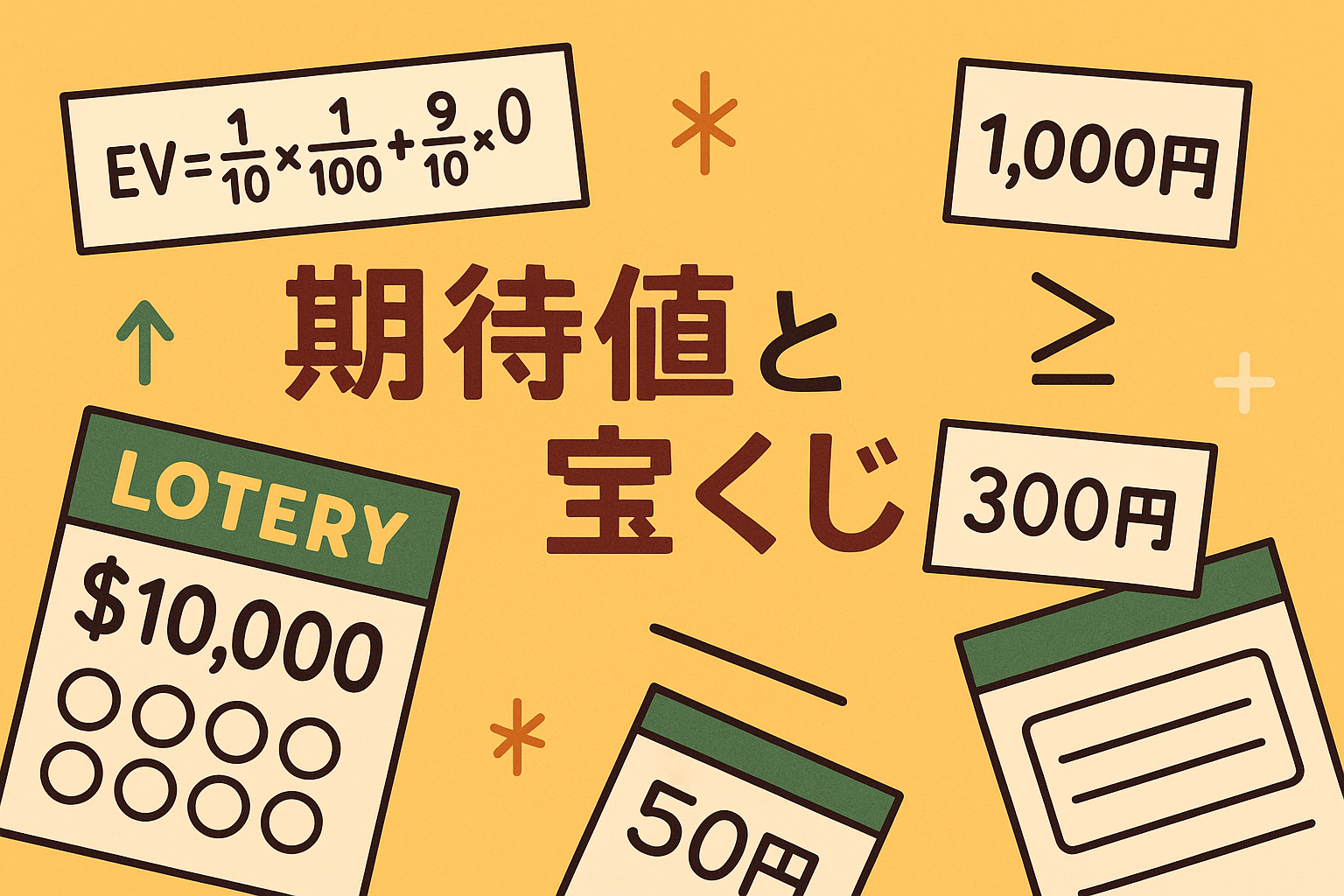
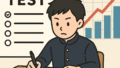
コメント