はじめに
2025年度1学期、6月上旬に行われた体育祭が終わった翌週のことでした。生徒たちは達成感と疲労が入り混じった様子で、授業への集中度はやや低下していました。
そんな時期に、数学Ⅱ「図形と方程式」の公式確認を行う際、Quizizz(今はWayground)というゲーミフィケーション型学習ツールを使って「10分間のミニアクティビティ」を実施しました。(実際のクイズはこちら)
本単元はパターン化された公式が多く、覚えてしまえば計算はスムーズですが、意味理解が伴わないと応用でつまずくという特徴があります。そこで、ゲーム感覚で公式の形と使い方を素早く想起できるようにしつつ、体育祭後の緩んだ空気を引き締める効果も狙いました。
ゲーミフィケーションを授業に取り入れる理由
ゲーミフィケーションとは
ゲーミフィケーション(Gamification)とは、教育やビジネス、日常生活などの非ゲーム的な場面に、ゲームの要素や仕組みを導入してモチベーションや行動を促す手法です。
教育分野での主な特徴は次の通りです。
- スコアやランキングによる競争心の喚起
- 即時フィードバックによる達成感の提供
- バッジや称号などの報酬システムによる継続意欲の向上
今回使用したQuizizz(Wayground)はこれらの要素を備えており、生徒がスマートフォンやPCを使って参加するだけで、問題ごとの正答率や順位がリアルタイムに表示されます。
理論的背景
教育心理学の自己決定理論(Deci & Ryan)では、動機づけは大きく内発的動機づけ(学ぶこと自体の楽しさ)と外発的動機づけ(報酬や評価のために学ぶ)に分けられます。
ゲーミフィケーションは外発的動機づけに分類され、学習行動の「きっかけづくり」として有効です。ただし、長期的な学習習慣につなげるためには、その後に内発的動機づけへと接続する仕掛けが必要です。
授業の概要
実施概要
項目詳細対象高校2年生(文理混合クラス)単元数学Ⅱ「図形と方程式」実施時期体育祭翌週(6月中旬)実施形態授業中の10分間に組み込み参加人数約30名
学習目標
本活動では、以下の3つの学習目標を設定しました。
- 知識の確認:公式の形を正確に想起できる
- 理解の深化:適用場面を区別できる
- メタ認知の促進:間違えた問題の原因を把握する
事前説明とルール
授業冒頭に次のことを明確に伝えました。
- 今回の活動は評価には関係しない(安心して参加できるように)
- 回線トラブルで参加できない場合は隣の生徒の画面を見てもよい
- 競争は楽しむ程度で、間違えた問題の復習が最も重要
この事前説明により、生徒は気楽に参加でき、クラス全体の雰囲気が和らぎました。
実施の流れ
短い導入(2分)
黒板とGoogleスライドで本日の公式一覧を提示しました。
対象公式(約10種類)
- 2点間の距離公式
- 中点の座標
- 直線の傾き・方程式
- 2直線の交点の求め方
- 点と直線の距離公式
- 円の方程式と接線の方程式
参加準備(1分)
生徒はQRコードからQuizizz(Wayground)にアクセスし、ニックネームを入力(何でもOK)しました。一部の生徒は回線の関係で接続できなかったため、隣の生徒とペアで画面を共有して参加しました。
実施(10分)
テンポよく問題を進めるため、1問あたりの制限時間は30秒に設定しました。
観察された生徒の反応
- 正解すると「よし!」と笑顔になる生徒
- 間違えるとすぐに隣と相談して解法を確認する姿
- 特に「点と直線の距離公式」での誤答が目立った
接続できなかった生徒も、ペアで参加することで孤立することなく活動に加われました。
結果共有とフィードバック(5分)
Quizizzの分析画面で問題別正答率を提示し、正答率の低かった公式は板書で簡単に解説しました。
具体例:「点と直線の距離公式」では、ルート内の式の取り扱いを間違えるパターンが多かったため、公式の成り立ちを簡単に確認しました。
実践の成果と課題
成果
学習意欲の向上
- 体育祭後の集中力が低下した時期でも、教室が活気づいた
- 授業後、「またやりたい」という声が多く聞かれた
インクルーシブな学習環境
- 回線不調の生徒も、ペア参加で全員が活動できた
- 競争に不安を感じる生徒も、気楽に参加できた
効果的なフィードバック
- 正答率データに基づき、弱点分野をその場で補強できた
- 個々の理解度を即座に把握することができた
課題
理解の深さへの懸念
- ゲーム形式に集中しすぎて、意味理解が浅くなる可能性
- 瞬発的な記憶に依存し、概念の本質理解が不十分になるリスク
動機づけの質
- 外発的動機づけ中心のため、継続学習に直結しない危険
- ゲーム要素なしの通常授業への意欲低下の可能性
技術的制約
- 接続環境の差が学習体験の均一性に影響する
- デバイス操作に不慣れな生徒への配慮が必要
ゲーミフィケーションの限界と対策
限界の認識
Quizizzはあくまで学習意欲を引き出す「入り口」であり、それ自体が理解や応用力を保証するものではありません。
効果的な活用のための工夫
以下の段階的なアプローチを実施しました。
- 現状把握:ゲームで知識の定着度を確認
- 深化学習:間違えた問題を授業や宿題で深掘り
- 応用展開:次回授業で応用問題に接続
継続的な学習への接続
ゲーミフィケーションの効果を持続させるため、以下の工夫を行いました。
- 活動後の振り返りシートで学習内容を整理
- 間違えた公式の個別練習問題を配布
- 次回の小テストでフォローアップを実施
教育的意義と今後の展望
教育的価値
本実践は以下の教育的価値を示しました。
多様な学習スタイルへの対応
従来の講義形式だけでなく、参加型の学習機会を提供
即時的な学習効果の確認
リアルタイムデータによる客観的な理解度把握
協働学習の促進
ペア参加により、自然な教え合いの場を創出
今後の改善点
内発的動機づけとの連携
ゲーム要素と概念理解をより効果的に結びつける方法の検討
評価方法の改善
ゲーミフィケーションの学習効果を測定する指標の開発
技術環境の整備
より安定した接続環境の確保とデジタルデバイド対策
まとめ
今回のQuizizz(Wayground)活用は、授業のわずか10分間でも効果的に学習意欲を高め、公式の定着度を確認できることを示しました。
評価に関係しない活動であったため、生徒は安心して参加でき、回線トラブルにも柔軟に対応できました。特に、体育祭後という特殊な時期において、学習への関心を再び喚起する効果は顕著でした。
ゲーミフィケーションは「楽しい」だけで終わらせず、その後の深い学びにつなげる設計こそが重要であることを改めて実感しました。今後も、生徒の多様なニーズに応える学習環境の構築に向けて、ICTツールの効果的な活用を模索していきたいと考えています。

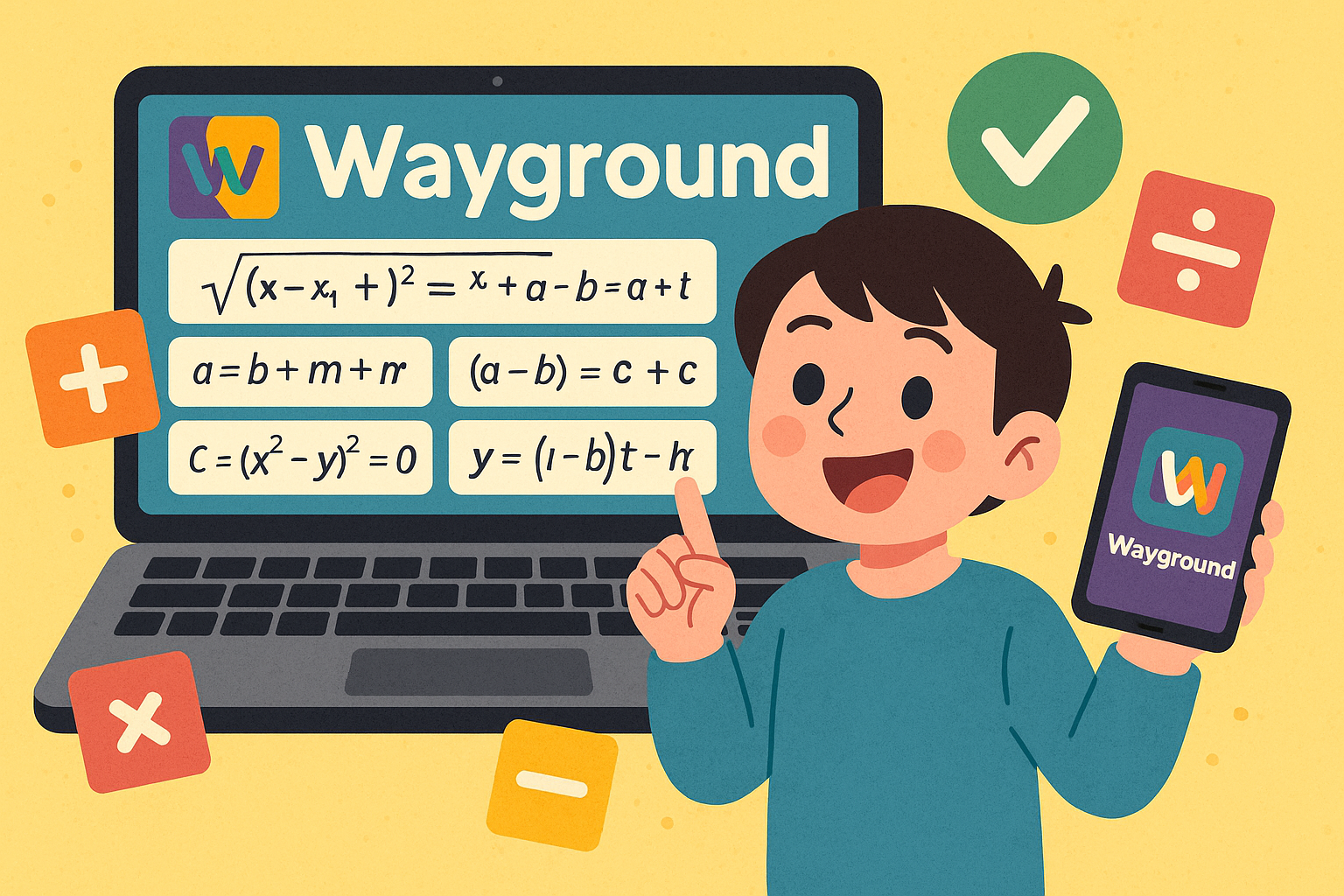


コメント