高2ベネッセ総合学力テストの位置づけ
高校2年生のベネッセ総合学力テストは、年間3回すべて記述式で実施されます。高1と大きく異なるのは出題範囲と科目構成であり、試験時間は高1と同じく数学100分です。
高1との主な違い
出題範囲の拡大 数学Ⅱ・数学B(またはC)が中心となり、高1の内容も複合的に出題されます。
A方式/B方式の分岐
- A方式:高1で数学Ⅰのみ履修 → 高2で数学Ⅱ+数学A
- B方式:高1で数学Ⅰ・A履修 → 高2で数学Ⅱ+数学B(またはC)
一般的な高校ではB方式を選択します。
科目数の増加 高2は10月模試から理科・社会も同日実施となり、総合的な学習計画が必要となります。
年間の数学指導スケジュール(数Ⅱ+数B・C)
【4〜6月】基礎固め+記述型への慣れ
目標:6月模試で記述式の解答形式を確立
学習内容
- 数Ⅱ:式と証明、複素数と方程式、図形と方程式
- 数B/C:数列(基礎)、ベクトル(基礎)
指導の工夫
- A方式は特に数A分野を先行して補強します
- 問題用紙に途中式を丁寧に記録する習慣を定着させます
- 自己採点・反省シート(Google Form等)で改善点を継続的に記録します
【7〜10月】応用力の育成+融合問題対応
目標:10月模試で証明・融合問題の得点力を向上
学習内容
- 数Ⅱ:指数・対数関数、三角関数(基礎・応用)、微分法
- 数B/C:数列応用、ベクトル応用
指導の工夫
- B方式はベクトル+数列の融合問題、A方式は確率分野を強化します
- 10月模試から理社が追加されるため、学習時間配分のシミュレーションを行います
【11〜1月】総合力+時間配分の完成
目標:複数分野の融合問題に対応し、安定した得点力を確保
学習内容
- 数Ⅱ:積分法(面積・体積)、微分積分の応用
- 数B/C:空間ベクトル、複素数平面の応用
指導の工夫
- 実際の模試時間を想定した演習を複数回実施します
- 分野ごとの得点目標を設定し、弱点分野を重点的に補強します
模試活用の指導ポイント
解答の記録と自己採点体制の構築
解答は必ず問題用紙に書き残すことを徹底します。返却まで約1か月を要するため、試験直後の自己採点を可能にすることが重要です。
誤答分析の体系化
自己採点後は誤答を「知識不足」「計算ミス」「論理の飛躍」に分類し、具体的な改善策を立てます。
データ管理による学習の可視化
Google Form等を活用して得点推移と改善計画を記録し、個別指導の資料として活用します。
全科目バランスを意識した学習計画
10月からは理科・社会も加わるため、数学の学習時間配分を調整し、全科目のバランスを考慮した計画を策定します。
各時期における重点指導事項
6月模試に向けて
記述式解答の基本形式を身につけることを最優先とし、途中過程の記述方法を丁寧に指導します。
10月模試に向けて
融合問題への対応力を高めるとともに、理科・社会の追加による時間的制約を考慮した学習戦略を確立します。
1月模試に向けて
高2内容の総仕上げとして、複数分野にわたる応用問題への対応力を完成させ、高3への橋渡しを行います。


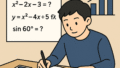
コメント